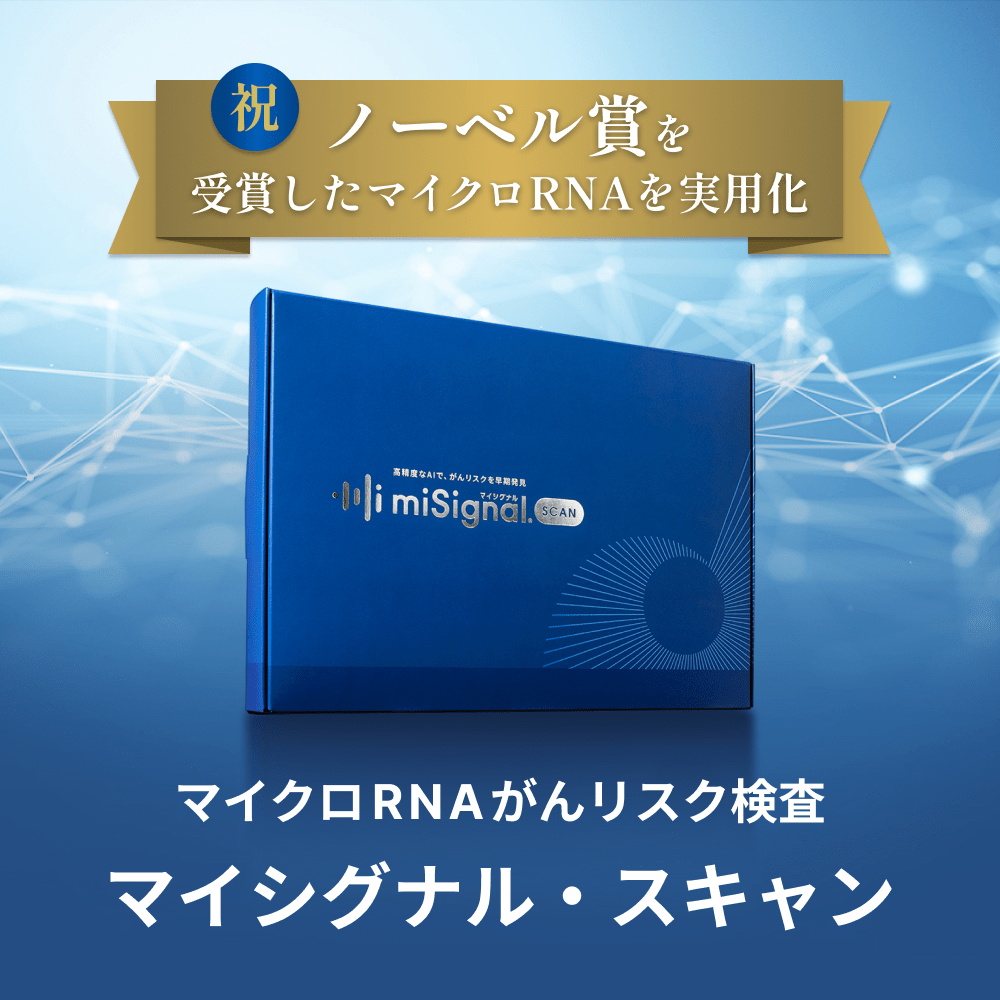がんの症状
生活習慣とがん
がんの基礎情報
【早期発見が大切】がんの種類・リスク因子・見逃せない症状を解説
- 公開日: 8/25/2025
- |
- 最終更新日: 8/25/2025

がんと聞くと、怖い・不安といった気持ちが先立つ方も多いのではないでしょうか。
しかし、どのような種類のがんがあるのかを知ることで、必要な備えや行動がとりやすくなります。
本記事では、日本で多くみられるがんの種類とそれぞれの特徴、早期発見の重要性についてわかりやすく解説します。
自分や家族の健康を守るために、まずは「がんを知る」ことからはじめてみましょう。
目次
がんの定義と種類について

細胞の遺伝子に生じた「変異」が原因で、細胞が制御を失い際限なく増え続ける塊が「腫瘍」です。
この腫瘍のうち、周囲の正常な組織へ広がるだけでなく、血液やリンパの流れに乗って体の別の部位へと移動し、そこで新たに増殖する性質を持っているのが「がん」です。
がんの種類は、肺に発生したら「肺がん」、胃に発生したら「胃がん」のように、主に最初にがんが発生した臓器や組織の名称で区別されます。
さらに、同じ臓器に発生したがんでも、その細胞のタイプや性質によって細かく分類されます。
*国立がん研究センター がん情報サービス がんという病気について
代表的ながんの種類
がんは、発生する臓器や細胞の種類によって、その特徴や治療法が大きく異なります。
ここでは、日本で比較的多くみられるがんについて、それぞれの主な特徴や注意点について解説します。
大腸がん
大腸がん@https://misignal.jp/article/colorectal-cancer-testは、日本人の罹患数第1位のがんで、S状結腸や直腸にできやすいといわれています。
初期段階では自覚症状がほとんどなく、健康診断などで偶然発見されるケースも少なくありません。
大腸がんはほとんどが「腺がん」という種類に分類され、まれに「扁平上皮がん」や「腺扁平上皮がん」などもあります。
大腸がんは、がんが大腸内にとどまっている場合、5年相対生存率は97.3%と高い数値を示しています。このことから、大腸がんは早期に見つけることができれば、比較的予後が良好ながんであるといえるでしょう。
多くの場合、良性のポリープが大腸がんへ進行すると考えられており、定期的な内視鏡検査によるポリープ切除が予防にもつながります。
肺がん
肺がん@https://misignal.jp/article/lung-cancer-testは、日本人のがんによる死亡数の第1位を占めています。
原因の70%は喫煙で、そのほかに受動喫煙やアスベストなどもリスクを高めるとされています。
肺がんの種類は大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」にわけられます。非小細胞肺がんに含まれる「腺がん」が、肺がんのなかで最も多くみられます。
肺がんは初期に症状が出にくく、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。そのため、定期的にがん検診を受け、リスク因子がある場合専門医への相談をおすすめします。
*一般社団法人 日本呼吸器学会 肺がん(1)概要と検査・診断
*国立がん研究センター がん情報サービス 肺がん 予防・検診
胃がん
胃がん@https://misignal.jp/article/stomach-cancer-testは、かつて日本で最も罹患数が多かったがんです。
ピロリ菌の感染や喫煙、過度の飲酒、塩分の摂りすぎなどがリスク要因とされています。近年はピロリ菌の感染率の低下や、除菌治療の普及などにより、罹患数は減少傾向です。
胃がんは、9割以上が胃の粘膜から発生する「腺がん」という種類です。腺がんは、細胞の増え方によって大きく以下の2つにわけられます。
| 分化型胃がん | 未分化型胃がん | |
| 特徴 | 比較的まとまって増殖する | バラバラに広がるように増殖する |
| 好発年齢 | 高齢者に多い | 若者も発症する |
未分化型胃がんには、胃の壁全体に硬く染み込むように広がり、進行が早いことで知られる「スキルス胃がん」が含まれます。
胃がんは、胃内視鏡検査や胃部X線検査が早期発見に有効であり、早期であれば内視鏡による治療も可能です。
*日本医師会 胃がんの原因|知っておきたいがん健診
*東京医科大学病院 胃がんの基礎知識
*がん研有明病院 胃がんの内視鏡治療と成績
乳がん
乳がん@https://misignal.jp/article/breast-cancer-symptoms-n-causesは、日本人女性の罹患数第1位のがんです。
女性ホルモンであるエストロゲンとの関連が深く、エストロゲンを含む経口避妊薬や、ホルモン補充療法が乳がんのリスクを高めることが知られています。その他のリスク因子として、飲酒・生活習慣・糖尿病の既往・遺伝的要因などがあげられます。
男性が発症するケースもありますが、乳がん全体の1%程度です。
乳がんの種類とそれぞれの特徴は、以下の通りです。
| 乳がんの種類 | 特徴 |
| 非浸潤がん | がん細胞が乳管や腺葉内に留まっている乳がん全体の約20%を占める |
| 浸潤がん | がん細胞が乳管の外に広がり、しこりとして触れる乳がん全体の約80%を占める |
| パジェット病 | 乳管のがんが皮膚まで広がって生じたもの主に乳頭に発生する乳がん全体の1〜2%を占める |
乳がんの早期発見には、月に一度のセルフチェックと、定期的な乳がん検診(マンモグラフィー・乳腺超音波検査)が有効です。
*国立がん研究センター がん情報サービス 乳がん 予防・検診
*国立がん研究センター 希少がんセンター 男性乳がん
前立腺がん
前立腺がんは、日本人男性の罹患数第1位のがんです。
ほかのがんと比較してゆっくりと進行することが多く、早期に発見できれば予後が良いとされるがんのひとつです。
前立腺がんのリスクは、年齢や家族歴に影響を受けます。年齢が上がるとともにリスクは高くなり、50歳以上の男性に多くみられます。
また、親や兄弟などに前立腺がんの経験者がいる場合は、そうでない方と比べて発症リスクが約2倍高まることが知られています。
前立腺がんの多くは腺がんで、悪性度を細胞の形や増え方で評価します。前立腺がんの早期発見には、血液検査で測定する「PSA」が有用とされており、50歳以上の男性は定期的なPSA検査が推奨されます。
*国立がん研究センター がん情報サービス 前立腺がんについて
膵臓がん
膵臓がん@https://misignal.jp/article/pancreatic-cancer-testは、他のがんと比較して進行が早く、早期発見が難しいがんです。リスク因子として、喫煙・糖尿病・慢性膵炎・膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN@https://misignal.jp/article/ipmn)・遺伝的要因などが知られています。
膵臓がんにはさまざまな種類がありますが、そのなかでもとくに代表的なものとして、以下の3つがあげられます。
| 膵臓がんの種類 | 特徴 |
| 浸潤性膵管がん | 膵臓がんの約90%を占める周囲の組織に浸潤しながら進行する |
| 腺房細胞がん | 膵臓がん全体の約0.3%程度を占める。周囲組織への浸潤は比較的少ない |
| 粘液産生膵がん | 粘液を産生する膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)などががん化したもの粘液が詰まることで膵炎のような症状を引き起こすこともある |
これらは、多くが「腺がん」に分類されます。
現時点では、国が推奨する確立された膵臓がんの検診はありません。このことも、膵臓がんの早期発見が難しい要因のひとつです。
*浜松医療センター 膵がんおよびその他の膵腫瘍
*国立がん研究センター 希少がんセンター 希少な肝胆膵がん
卵巣がん
卵巣がん@https://misignal.jp/article/ovarian-cancer-testsは、女性の卵巣に発生するがんで、初期には自覚症状がほとんどありません。発見が遅れることが多いことから、「サイレントキラー」とも呼ばれています。
卵巣がんは主に40代以降の女性に多くみられますが、年齢に関わらず発症する可能性があります。そのほかのリスク因子として、閉経・子宮内膜症・妊娠出産経験が少ない・遺伝的要因などがあげられます。
卵巣がんの種類は、発生する組織によって以下に分類されます。
| 卵巣がんの組織型 | 特徴 |
| 漿液性がん | 高異型・低異型にわけられる高異型は進行が早い |
| 明細胞がん | 早期の段階でみつかりやすい子宮内膜症由来が多い |
| 類内膜がん | 子宮内膜症由来が多い |
| 粘液性がん | 若年者に発生することもある腫瘍が10cmを超えることもある |
卵巣がんの検診は、現時点で確立されていません。卵巣がんのリスクが高い場合は、婦人科での定期的な検査をおすすめします。
*日本婦人科腫瘍学会 卵巣がん治療ガイドライン2015年版 第2章 卵巣癌
がんのリスクを高める要因
がんの発症にはさまざまな要因が関係しており、日常生活のなかで意識することでリスクを抑えることも可能です。
まずは、がんにどのような背景があるのかを正しく知り、自分にとって気をつけるべきポイントを見極めていきましょう。
生活習慣
がんのリスクを高める大きな要因として、バランスの悪い食生活・運動不足・喫煙・過度な飲酒などがあげられます。
とくに喫煙は、肺がんをはじめ、食道がん@https://misignal.jp/article/esophageal-cancer・胃がん・膵臓がんなど、全身のさまざまな部位のがん発生と深く関連しています。また、過度な飲酒も、肝臓がんや食道がん、大腸がんなどのリスクを高める要因です。
食生活も非常に重要です。野菜や果物が少なく、加工食品や赤肉、塩分の多い食事に偏っていると、胃がんや肺がんなどのリスクが上がるといわれています。
がんを予防するためには、日々の生活習慣を見直し、小さな選択を積み重ねていくことが大切です。
*国立がん研究センター がん情報サービス 科学的根拠に基づくがん予防
感染
特定のウイルスや細菌への感染は、日本人のがんの原因の約20%を占めます。
細菌やウイルスが体内に長くとどまることで、慢性的な炎症を引き起こしたり、感染体が作り出すがん原性タンパク質が直接作用したりして、がんの発生につながることがあるのです。
感染が原因となって発症する可能性があるがんには、次のような種類があげられます。
| がんの種類 | 原因となる細菌・ウイルス |
| 子宮頸がん | ヒトパピローマウイルス(HPV) |
| 胃がん | ヘリコバクター・ピロリ(ピロリ菌) |
| 肝臓がん | B型肝炎ウイルスC型肝炎ウイルス |
これらのウイルスや細菌に感染したからといって、必ずしもがんを発症するわけではありません。
しかし、適切な予防接種を受けたり、感染がわかった場合早期に治療を受けたりすることで、がんのリスクを低減できる可能性があります。
*国立がん研究センター がん情報サービス 科学的根拠に基づくがん予防
遺伝的要因と家族歴
がんは細胞の遺伝子に生じる「変異」が原因で発生しますが、変異の一部が親から子へと受け継がれることがあります。
とくに乳がんや卵巣がん、大腸がんなど、一部のがんでは遺伝的な影響が比較的強くみられます。
そのため、血縁者にがんの経験者がいる「家族歴」がある場合、そうでない方に比べてがんを発症するリスクが高まる可能性があります。しかし、家族にがんの経験者がいるからといって、必ずしもご自身もがんになるわけではありません。
過度な心配はせず、家族歴がある方は、より積極的に定期的な検診を受けることをおすすめします。
気になる症状とがんの関連性
早期のがんでは自覚症状が現れにくいですが、体は小さなサインを出している場合があります。
ここでは、見逃しがちな症状と、関連があるがんの種類について解説します。
血尿・排尿時の違和感
血尿や排尿時の違和感は、膀胱がんや腎臓がん、男性では前立腺がんなどの重要なサインである可能性があります。
尿に血液が混じる「血尿」は、肉眼で確認できる場合もあれば、健康診断などで尿潜血としてはじめて指摘されることもあります。
また、排尿時の痛みや頻尿、尿が出にくいといった、排尿に関する違和感が長く続く場合も注意が必要です。
こうした症状は、尿路感染症や前立腺肥大症などでも起こります。しかし、がんが原因である可能性も否定できないため、自己判断せずに泌尿器科を受診するようにしましょう。
長引く咳や息切れ
風邪や喘息、アレルギーではないのに、咳が2週間以上続く、または息切れしやすいと症状がある場合は、肺がんの可能性も考えられます。
とくに、喫煙習慣のある方はリスクが高まるため要注意です。初期のがんは風邪の症状とよく似ており、見過ごされることもあります。
がんが進行すると呼吸が苦しくなったり、痰に血が混じったりすることもあります。
*日本癌治療学会 がん診療ガイドライン 肺癌診療ガイドライン2021年版第1部(肺癌の分類〜Ⅱ)
しこりや皮膚の変化
体にできるしこりや皮膚の変化は、見逃されやすいがんのサインのひとつです。
たとえば、乳房や首、わきの下、足の付け根などに硬いしこりが触れる場合は、乳がんや悪性リンパ腫などの可能性があります。
また、皮膚の一部が黒ずんだり、ほくろの形がいびつだったりする場合は、皮膚がんの兆候かもしれません。
早期発見によってがんの予後は大きく改善する
がんは初期の段階で発見できれば、手術による切除だけで完治することも多く、体への負担は比較的少なくすみます。
しかし、初期段階では症状が現れていないことも多く、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。
がんが進行して広がっていたり、他の臓器に転移してしまったりすると、治療の選択肢が限られ、予後も悪くなってしまうでしょう。
そのため、症状がなくても定期的に検診を受け、少しでも気になる体の変化があればすぐに医療機関を受診したりすることが大切です。
不安を感じたときのファーストステップ
がんに対する不安を感じたとき、「何をすればいいのかわからない」「病院に行くべきか迷ってしまう」という方も多いでしょう。
ここでは、不安を感じたときに取るべき最初の一歩についてご紹介します。
医療機関を受診するタイミング
「これって大丈夫かな」と思う症状があっても、病院に行くほどではないと自己判断してしまう方は少なくありません。
しかし、体からのサインを見逃すと、がんが進行してしまうリスクもあります。
早期のがんは明らかな症状が出にくいぶん、少しの違和感が重要な手がかりになることがあります。
血尿や長引く咳、体のしこりなど、日常生活に支障がなくても気になる症状がある場合は、医療機関を受診しましょう。
自宅でできるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」
「忙しくて病院に行く時間がない」「今すぐに病院に行くほどではないけれど、がんの可能性が気になる」という方には「マイシグナル・スキャン」がおすすめです。
マイシグナル・スキャンは、膵臓・大腸・肺・胃・乳房・卵巣・食道・膀胱・前立腺・腎臓の10種類のがんリスク※を、ステージ1から検出できる検査です。
検査の方法は簡単で、自宅で尿を採取して送るだけ。痛みや食事・運動の制限もないため、忙しい方でも負担なく受けられます。
結果はがんリスクの有無を可視化してくれるため、必要に応じて生活改善や医療機関の受診など、次の行動につなげられます。
がんに対する不安がある方は、マイシグナル・スキャンを活用して、「たぶん大丈夫」を根拠ある自信に変えてみませんか。
※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
日々の意識と行動でがんのリスクは減らせる
本記事では、日本でよくみられるがんの種類や症状のサイン、発症リスクを高める要因について解説しました。
がんは誰にとっても他人事ではなく、年齢や性別を問わずなりうる病気です。
がんの特徴やリスク因子を知っておくことで、予防・早期発見に向けて具体的な行動を起こせるでしょう。
忙しい方や、病院に行くべきか悩んでいる方には、自宅で手軽にがんリスクを確認できる「マイシグナル・スキャン」という選択肢もあります。
がんと向き合う第一歩として、今日からできることを生活に取り入れてみてください。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター
急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。
自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆
カテゴリから探す
キーワードから探す