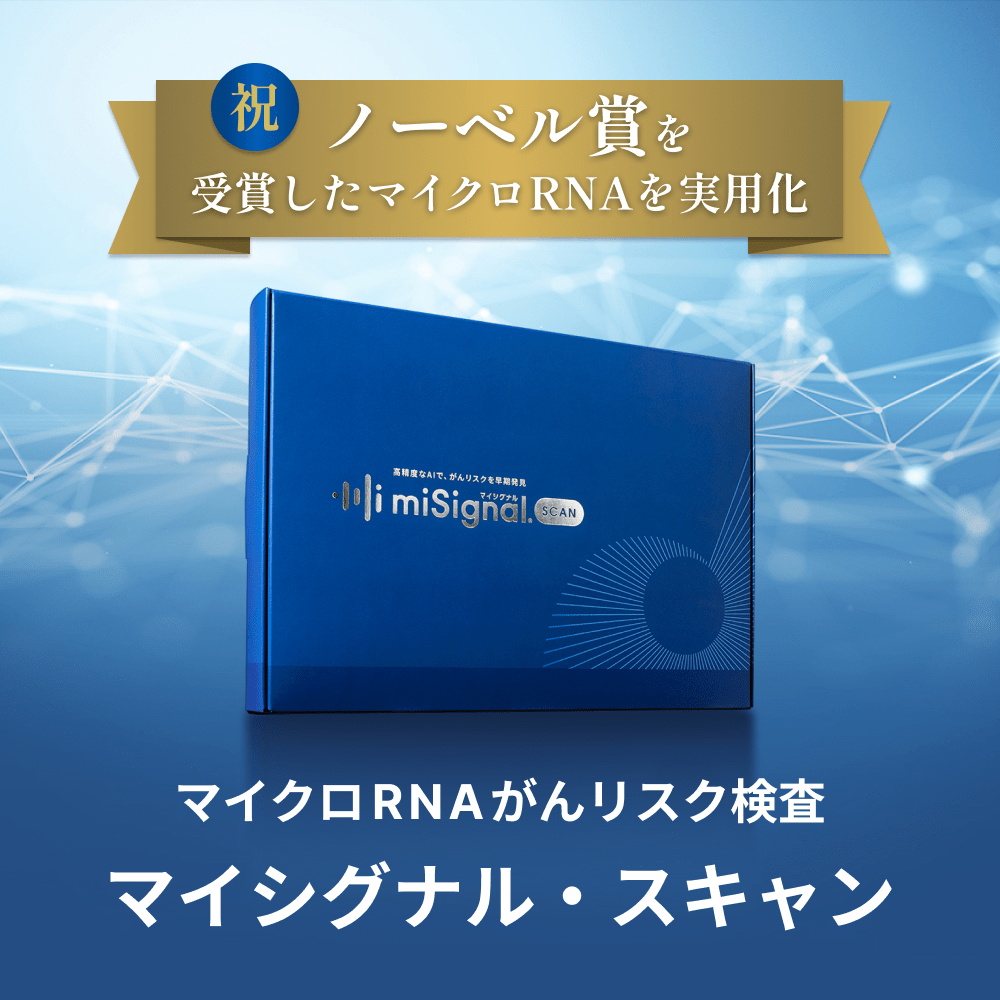がん検査
がん検査は症状が出る前に!種類やとくに受けるべき人の特徴を解説
- 公開日: 8/25/2025
- |
- 最終更新日: 8/25/2025

「がん検査は、症状が出てから受ければいい」と思っていませんか?
実は、がんの多くは初期に自覚症状がほとんどなく、気づいたときには進行しているケースも珍しくありません。
とくに膵臓がんや卵巣がんなどの早期発見が難しいがんは、見逃すと治療が困難になることも。
そこで本記事では、がん検査の種類や受けるべき人の特徴、自宅で手軽にがんリスクをチェックできる検査について詳しく解説します。
がんを「他人ごと」にせず、自分ごととして健康を見直すきっかけにしてください。
目次
がんは決して他人ごとではない

がんは日本人の死亡原因の第1位を占めており、2人に1人が一生のうちに一度はかかるといわれています。
多くの方が「自分とは関係ない」「まだ若いから大丈夫」などと考えがちですが、がんは年齢を問わず発症する可能性があります。
また、がんの多くは初期段階でほとんど自覚症状が出ないため、気づいたときには進行していたというケースも少なくありません。
日常のなかで「少し体調が悪いな」と感じる程度の変化が、実は重大なサインである可能性もあります。
だからこそ、「自分は大丈夫」と油断せず、早期発見できるよう定期的ながん検査を受けることが大切です。
がん検診や検査を受けるべき2つの理由
がんは誰にでも起こりうる病気だからこそ、定期的ながん検査が重要です。
ここでは、がん検査を受けるべき理由を、2つの視点からわかりやすく解説します。
自覚症状が出にくいがんが多いから
多くのがんは、初期の段階ではほとんど自覚症状が現れません。
痛みや違和感が現れたときにはすでに進行しているケースも多く、「体調が悪くなってから病院に行けばいい」と思っていると、手遅れになることもあります。
とくに、膵臓がんや卵巣がん、大腸がんなどは、進行するまで症状がわかりにくく、気づいたときには他の臓器に転移していることもあります。
自覚がないうちに進行している可能性があるからこそ、症状が出る前から検査を受けるようにしましょう。
早期発見で治療効果が高まるから
がんは発見される時期によって、治療方法や効果に差が生まれます。
早期に見つかった場合、治療による身体的・経済的な負担が軽くなるだけでなく、生存率も大幅に高まります。
たとえば大腸がんの場合、早い段階のステージ1で見つかれば、5年生存率は83.1%と非常に高いです。ところが、発見が遅れてステージ4まで進行してしまうと、5年生存率は17.0%まで下がってしまいます。
早期に見つかって治療期間が短く済めば、仕事や生活への影響も抑えられるでしょう。たとえがんが見つかったとしても、早い段階なら生活の質を保ちながら治療を進められます。
そのためにも、症状が出る前から定期的に検査を受けておくことが非常に重要です。
がん検査をとくに受けたほうがいい人の特徴
がんは誰にでも起こりうる病気ですが、なかでも発症リスクが高い方には、早めの検査が推奨されます。
ここでは、がん検査をとくに受けたほうがいい方の特徴をご紹介します。
家族にがん患者がいる
家族のなかにがん経験者がいる場合、自分自身ががんを発症するリスクも高まる可能性があります。
とくに、親や兄弟といった近い血縁者にがん患者がいる場合は、遺伝的な要因が関係していることも少なくありません。
実際に、一部の乳がんや卵巣がん、大腸がんなどは、遺伝的要因により家族内で発症しやすいといわれています。
家族のなかにがん経験者が複数いる場合は、たとえ症状がなくても、若いうちから定期的に検査を受けることが大切です。
生活習慣が乱れている
がんリスクを高める生活習慣として、以下のような要因があげられます。
- 食生活
- 運動不足
- 喫煙
- 過度な飲酒
特定のがんは、このような生活習慣と密接に関係しています。たとえば喫煙は肺がん、過剰な飲酒は食道がんや肝臓がんのリスクを高めることがわかっています。
また、加工食品の摂取が多く、野菜や果物が不足している食生活も、がんのリスクが高まる要因のひとつです。
「まだ若いから大丈夫」と思っていても、生活習慣が乱れている自覚があるなら、検査を通じて自分の健康状態を見直すきっかけにしましょう。
*国立がん研究センター がん情報サービス 科学的根拠に基づくがん予防
がんを発症しやすい年齢に達している
がんは、年齢とともに発症リスクが高まる病気です。
たとえば、日本人男性の罹患数第1位である前立腺がんは、50代以降で急激に増え、70代でピークを迎えます。
忙しいと体調の変化を見過ごしてしまいがちですが、年齢とともに定期的ながん検査を習慣化していくことが大切です。
症状がないうちにがん検査を受けておくことで、万が一がんが見つかったとしても早期に対応でき、生活の質を損なわずに治療に取り組むことができます。
代表的ながん検査の種類
がんのスクリーニングや診断には、目的やがんの種類に応じたさまざまな検査方法が用いられます。
ここでは、代表的ながん検査の種類とその特徴について、わかりやすく解説します。
血液検査
がんの血液検査では、主に「腫瘍マーカー」を測定します。
腫瘍マーカーは、がん細胞が体内に存在するときに血液中に分泌される、特定のタンパク質や酵素などの物質を指します。
それぞれのがんに対応する腫瘍マーカーは、以下の通りです。
| がんの種類 | 主な腫瘍マーカー |
| 甲状腺がん | CEA |
| 非小細胞肺がん | CYFRA21-1、CEA、SLX、CA125、SCC |
| 小細胞肺がん | NSE、ProGRP |
| 食道がん | SCC、CEA |
| 胃がん | CEA、CA19-9 |
| 大腸がん | CEA、CA19-9、p53抗体 |
| 肝臓がん(肝細胞がん) | AFP、PIVKA-Ⅱ、AFP-L3 |
| 胆道がん | CA19-9、CEA |
| 膵臓がん | CA19-9、Span-1、DUPAN-2、CEA、CA50 |
| 膀胱がん | NMP22、BTA |
| 前立腺がん | PSA |
| 乳がん | CEA、CA15-3 |
| 子宮頸がん | SCC、CA125、CEA |
| 卵巣がん | CA125 |
出典:国立研究開発法人国立がん研究センター がん情報サービス「腫瘍マーカー検査とは」
ただし、これらの数値が高いからといって、必ずしもがんであるとは限りません。炎症や他の病気でも上昇することがあります。
そのため、腫瘍マーカー検査は単独での診断には向かず、がんのスクリーニングや、治療後の経過観察を目的として実施します。
画像検査
画像検査は、体内のがんの有無や位置、大きさを視覚的に確認するために重要な検査です。
代表的な画像検査として、以下があげられます。
| 画像検査 | 特徴 |
| エコー(超音波検査) | 体表から超音波をあて体内をリアルタイムで観察痛みがなく非侵襲的 |
| レントゲン(単純X線検査) | がんの有無や形を確認肺・骨・腹部などに有用 |
| CT(コンピュータ断層撮影) | 連続した断面の画像を作成し身体を立体的に把握がんの診断で基本となる検査 |
| MRI(磁気共鳴画像) | 強力な磁石と電波で磁場を発生させて行う検査正常な組織とがん細胞を区別しやすい |
| PET(陽電子放出断層撮影) | がん細胞の代謝の活性度を画像化一度の検査でほぼ全身を撮影できる脳や消化管などの一部の臓器では診断が難しい |
いずれも身体への負担は比較的少なく、検査は短時間で終了します。
これらの画像検査はそれぞれ得意とする情報が異なるため、組み合わせて実施することで、より正確な診断が可能となります。
*国立がん研究センター がん情報サービス それぞれの検査 種類別
内視鏡検査
内視鏡検査は、細い管状の内視鏡を体内に挿入し、消化管や気管支などの内部を直接観察する検査です。
先端にカメラが搭載されているため、モニターで詳細な画像を確認できます。
たとえば、食道・胃・十二指腸を調べる上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)や、大腸を調べる下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)などがあります。
異常が見つかった場合は、その場で組織の一部を採取(生検)し、病理検査に提出することで、がんであるかどうかの確定診断も可能です。
また、内視鏡の先端に超音波装置を搭載した超音波内視鏡検査(EUS)では、消化管の壁の奥にある病変や膵臓などの臓器を、より詳細に観察することもできます。
その他の検査
血液検査や画像検査、内視鏡検査のほかにも、がんの種類によっては以下のような検査もあります。
| がんの種類 | 検査項目 |
| 子宮頸がん | 子宮頸部の細胞診・内診 |
| 肺がん | 喀痰細胞診※ |
| 大腸がん | 便潜血 |
これらの検査は、それぞれのがんに特化しており、スクリーニングとして活用されることが多い傾向です。
自覚症状がなくても定期的に受けておくことで、がんの早期発見につながる可能性があります。
※50歳以上かつ喫煙指数(1日の喫煙本数×年数)600以上の方が対象
がんの検査はどこで受ける?費用感と補助制度
がん検査を受ける手段には、「健康診断」「人間ドック」「がん検診」「がん専門外来」などがあり、目的や内容が異なります。
それぞれのがん検査の特徴・費用感・助成制度について、以下にまとめました。
| 検査の種類 | 特徴 | 費用(自己負担)の目安 | 補助制度 |
| 健康診断 | 基本的な検査が中心でがん検査は限定的 | 0〜1万5,000円程度 | 会社員の場合は原則職場が全額負担 |
| 対策型がん検診 | 特定部位のがんの早期発見を目的とした公共的予防策 | 一部位につき500〜3,000円程度 | 自治体の助成あり |
| 人間ドック | 自由度の高い検査で、網羅的な検査も可能 | 3万〜10万円程度 | 一部補助がある場合あり(健保組合など) |
| 専門外来 | 自覚症状や既往歴がある場合の精密検査 | 2,000円〜2万円程度(保険適用) | 医師が医学的必要性を認めた場合に保険適用 |
自身のライフスタイルや、利用できる助成制度を考慮して、がん検査を日常に取り入れてみてください。
症状別に考えるがんの可能性と検査
初期のがんでは自覚症状が出にくいこともありますが、以下のようなサインが現れる場合もあります。
| 症状 | 可能性があるがんの種類 |
| 疲れやすい・倦怠感・発熱 | 白血病など血液系のがん |
| 長引く咳 | 肺がん |
| 原因不明の痛み・しこり | 乳がん・リンパ腫など |
| 血尿 | 膀胱がん・前立腺がん・腎臓がん |
| 女性器からの不正出血 | 子宮体がん |
上記のような症状が出ている場合は、自己判断で放置せず、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。
体からの小さな異変に早い段階から気づくことで、治療の選択肢を広げ、予後の改善にもつながります。
がん家系・不安な人におすすめしたい予防的検査
家族にがん経験者がいる場合や、将来的ながんリスクが気になる方には、予防的な検査を受けることで安心につながることもあります。
ここでは、遺伝子検査とがんリスクチェックの特長や、活用方法について詳しくご紹介します。
遺伝子検査
遺伝子検査では、生まれもった遺伝子情報をもとに、がんのなりやすさを調べる検査です。
家族にがんの発症者が多い場合は、がんの発症と関係している遺伝子に変異がある「遺伝性腫瘍」の可能性がります。
遺伝性腫瘍の代表的な例として、乳がんや卵巣がんに関連するBRCA1・BRCA2遺伝子の変異があります。
変異がある場合は、定期健診の頻度を高めるほか、予防目的で乳房や卵巣を切除する「リスク低減手術」という選択肢もあります。
ただし、遺伝性腫瘍の原因遺伝子に変異があるからといって、必ずがんになるわけではありません。
遺伝子検査は、一定の基準を満たせば保険適用となる場合もあります。家族にがん経験者が多くて不安な場合は、遺伝カウンセリングで疑問や心配なことを相談してみましょう。
がんリスクチェック
がんリスクチェックは、現在の体の状態から「いまのがんリスク」を評価する検査です。
尿や血液に含まれる特定の物質(バイオマーカー)を解析することで、がんリスクを確認できます。
身体的な負担が比較的少なく、自宅で手軽に行える検査も多いため、忙しい方や病院に抵抗がある方でもストレスなく受けられます。
現在のリスクを数値として把握することで、予防や早期発見に向けた具体的な行動のきっかけとなるでしょう。
がんリスクチェックなら「マイシグナル・スキャン」
がんは早期発見が何よりも重要ですが、「忙しくて病院に行けない」「症状が出てから病院へ行こうと思っている」といった理由で、検査のタイミングを逃してしまう方も少なくありません。
そのような方には、自宅で簡単にがんリスクを確認できる「マイシグナル・スキャン」がおすすめです。
マイシグナルスキャンには、以下の特徴があります。
- 最大10種類のがんリスクをまとめてチェック
- ステージ1の早期がんも高精度でリスク検出
- 自宅で手軽に検査可能
がんに対する漠然とした不安を解消したい方は、ぜひチェックしてみてください。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
最大10種類のがんリスクをまとめてチェック
マイシグナル・スキャンでは、1回の検査で最大10種類のがんリスク※を同時に検査できます。
対象となるのは、膵臓がん・肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・卵巣がん・食道がん・前立腺がん・膀胱がん・腎臓がんの10種類です。
がんの種類ごとに複数回検査を受ける必要がなく、1回の採尿でまとめてリスクを把握できるのが大きな特長です。時間や体への負担が少ないため、忙しい方でもストレスなく続けられるでしょう。
なかでも膵臓・卵巣・膀胱・腎臓・食道がんは有効な検診方法が確立されていないため、マイシグナル・スキャンでリスクを早めに知っておくことで、将来の安心につながります。
※卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります
ステージ1の早期がんも高精度で検出
マイシグナル・スキャンは、尿中に含まれるバイオマーカー「マイクロRNA」をAI技術で解析することで、がんのリスクをステージ1から検出します。
過去には、マイシグナル・スキャンがきっかけで、レントゲンには映らないほど小さなステージ0の肺がんを検出した事例もあります。
早期発見は治療成績の向上だけでなく、体への負担や治療費の軽減にもつながるでしょう。
症状が出る前に身体からのサインを捉える「マイシグナル・スキャン」は、予防医療の新たな可能性として注目されています。
自宅で手軽に検査可能
「マイシグナル・スキャン」は、医療機関に足を運ぶ必要がなく、自宅で完結する点が大きな魅力です。
キットを使用して尿を採取し、返送するだけで検査が完了します。
面倒な予約や待ち時間、検査中の身体的負担や制限も一切なく、自宅で自分の健康状態に向き合えるため、忙しい方や病院が苦手な方にもおすすめです。
万が一、検査結果が高リスクだった場合も、受診すべき診療科が明確にわかるため、次のステップに一歩踏み出しやすいでしょう。
健康管理の第一歩として、マイシグナル・スキャンによる定期的ながんリスクを選択肢に入れてみませんか。
症状が出る前に検査を受けてがんリスクを把握しよう
がん検査は、自覚症状が現れてから受けるものではなく、健康なうちにこそ積極的に取り組むべきものです。
がんの早期発見は治療の選択肢を広げ、身体的・経済的な負担を軽減するだけでなく、自分や大切な人の将来の安心につながります。
「まだ大丈夫」「忙しいからまた今度」と思っている方にこそ、負担の少ない方法で健康状態を見つめ直すことが大切です。
もし病院に行くハードルが高いと感じているなら、自宅で手軽にリスクを確認できる「マイシグナル・スキャン」を活用してみてください。
まずは自分の体の現状を知り、必要に応じて適切な医療機関と連携しながら、自分にあった方法で健康管理をはじめてみましょう。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国1500軒の医療機関でも導入されています。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター
急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。
自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆
カテゴリから探す
キーワードから探す