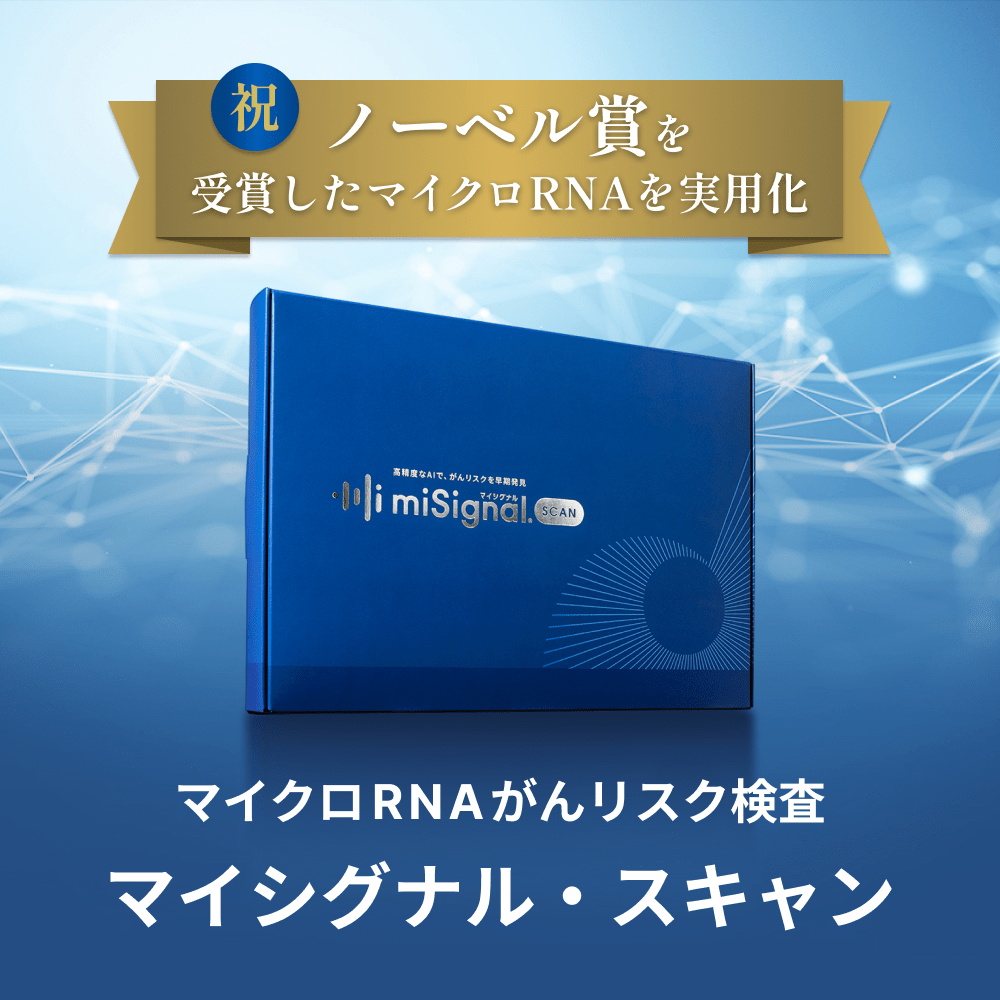がん検査
がんの症状
膀胱がんのステージ別生存率と治療法|早期発見で予後は変わる
- 公開日: 8/27/2025
- |
- 最終更新日: 8/27/2025

「膀胱がんと診断された」「家族ががんになった」「症状が出て不安」
そんなとき、気になるのが「どれくらい助かるのか」という生存率ではないでしょうか。
実際に膀胱がんは再発しやすく、進行度によって治療法や予後が大きく変わります。しかし、早期に発見できれば体への負担が少ない治療を選択でき、生活の質を保ちながら良好な経過を期待できるでしょう。
本記事では、膀胱がんのステージ別生存率と治療法、再発リスクを下げるための生活習慣や検査の活用方法をわかりやすく解説します。
膀胱がんに対して不安を抱いている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
膀胱がんとは?

膀胱がんとは、尿をためる役割を持つ膀胱にできるがんを指します。男性に多く、とくに50代以降から発症しやすくなります。
膀胱がんの90%以上は、膀胱の内側を覆う尿路上皮に発生する「尿路上皮がん」です。尿路上皮がんは、がんが膀胱の筋層に達しているかどうかによって「筋層非浸潤性がん」と「筋層浸潤性がん」に分類されます。
膀胱がんは、血尿や排尿時の違和感といった症状をきっかけに発覚することが多いですが、初期の段階では無症状のケースも少なくありません。そのため、健康診断や人間ドックで偶然見つかる場合もあります。
進行するとリンパ節や肺・肝臓・骨などへ転移する可能性もあるため、早期発見が非常に重要です。
*国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)(2021)
膀胱がんのステージ別5年生存率
膀胱がんのステージ別5年生存率は、以下の通りです。
| ステージ | 5年生存率 |
| 限局(ステージ0・1) | 87.3% |
| 領域(ステージ2・3) | 38% |
| 遠隔(ステージ4) | 9.5% |
数字だけを見ると不安になるかもしれませんが、実際には治療法の選択や生活習慣の工夫によって、その後の経過は変えられる可能性があります。
ここではステージごとの5年生存率を整理し、治療や予後の可能性についてわかりやすく解説していきます。
ステージ0・1|がんが膀胱内にとどまっている場合の生存率
ステージ0・1の膀胱がんは5年生存率が87.3%と比較的高く、治療によって良好な経過が期待できます。
この時期の膀胱がんは、腫瘍が膀胱内にとどまっており、筋層まで達していない段階です。
ただし、膀胱がんは再発しやすい性質を持っているため、治療後も定期的に膀胱鏡検査や尿検査を受け、経過をしっかり見守る必要があります。
ステージ2・3|がんが膀胱の周囲に広がっている場合の生存率
ステージ2・3の膀胱がんの5年生存率は38%であり、早期段階に比べて低下します。
この時期の膀胱がんは、腫瘍が膀胱の筋層にまで達しており、場合によっては膀胱の外側や周囲の臓器へ広がっている段階です。
治療には膀胱全摘除術や放射線治療、薬物療法を組み合わせることが多く、身体への負担も早期段階と比べて大きくなるでしょう。
ただし、適切な治療と継続的な経過観察を受けることで、再発や進行を抑えてより良い予後につなげられる可能性があります。
ステージ4|遠隔転移がある場合の生存率
ステージ4の膀胱がんの5年生存率は9.5%であり、他のステージと比べて大きく低下します。
この段階では、がんがリンパ節や肺・肝臓・骨などの遠隔臓器に転移しており、寛解を目的とした治療は難しいのが現状です。
手術でがんを取り除くのが難しい場合、薬物療法を行ってがんの増殖を抑えます。
薬物療法の効果がない場合や体力的に続けられない場合には、痛みや不快な症状を和らげる緩和ケアを行うこともあります。
膀胱がんのステージごとの治療法
膀胱がんのステージごとの治療法は以下の通りです。
| ステージ | 治療法 |
| ステージ0・1 | TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) 膀胱内注入療法 |
| ステージ2・3 | 膀胱全摘除術 放射線治療 TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) 薬物療法 |
| ステージ4 | 放射線治療薬物療法 |
膀胱がんの治療は、がんの進行度や患者さんの体調、そして生活の質をどう保つかによって選択肢が変わります。
膀胱がんの代表的な治療法と適応するステージについて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術)
TURBTは、膀胱がんの診断と治療を同時にできる手術で、主にステージ0・1の膀胱がんに行います。
尿道から内視鏡を挿入し、膀胱の内側にできた腫瘍を電気メスで切除します。体への負担が少なく、比較的早期に回復できるのが特徴です。
しかし、TURBTだけでは膀胱に残る微細ながん細胞を完全に除去できず、数年以内に再発するケースも少なくありません。
そのため、TURBTによる治療の後には、膀胱内注入療法を組み合わせて再発リスクを下げるのが一般的です。
膀胱内注入療法
膀胱内注入療法は、主にステージ0・1の膀胱がんに行う治療法です。
TURBTで腫瘍を切除した後に行うことが多く、膀胱に残っている可能性のあるがん細胞を攻撃し、再発リスクを下げる を防ぐ効果が期待できます。
以下の薬物を、尿道からカテーテルを通して膀胱の中に直接注入します。
| 薬物 | 対象リスク |
| 細胞障害性抗がん薬注入療法 | 低リスク中リスク |
| BCG(ウシ型弱毒結核菌)注入療法 | 中リスク高リスク超高リスク |
ただし、膀胱がんは再発しやすいため、膀胱内注入療法を行っても数年以内に再発する可能性があります。
膀胱全摘除術
膀胱全摘除術は膀胱をすべて摘出する外科的治療で、主にステージ2・3の膀胱がんに対して行います。
膀胱を摘出すると尿をためられなくなるため、同時に尿管皮膚ろう造設術や回腸導管造設術などの尿路変更術を行い、排尿機能を確保します。
膀胱全摘除術は寛解を目指せる一方で体への負担は非常に大きく、術後の合併症や生活の変化も避けられません。
さらに、膀胱に隣接する神経や組織に影響が及ぶことで、排尿機能だけでなく性機能にも影響が出る可能性があります。
放射線治療
放射線治療は、放射線を照射してがん細胞を縮小させる治療法です。
がんが進行したことによる膀胱出血や、骨転移による痛みなどの症状を和らげる目的で行うことがあります。
また、ステージ2・3で膀胱全摘除術が標準治療とされるケースでも、高齢者や心疾患・呼吸器疾患などの疾患があって膀胱全摘除術が難しい方に対して、放射線治療を行うことがあります。
膀胱温存を強く希望する場合に、TURBTや薬物療法と組み合わせて行うこともあります。
薬物療法
薬物療法は、薬物を体内に取り入れてがんの増殖や進行を抑える治療法で、主にステージ4の膀胱がんに対して行います。
膀胱がんの薬物療法は、主に以下の方法で行います。
| 薬物 | 特徴 |
| 細胞障害性抗がん薬 | がんの増殖や進行を抑える |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | がん細胞を攻撃する力を保つ |
| 抗体薬物複合体 | がん細胞を認識する抗体に抗がん薬を結合し、がん細胞だけを攻撃する |
ステージ2・3で膀胱温存を目指す場合にも、放射線治療やTURBTと組み合わせて薬物療法を行うこともあります。
ただし、薬の効果には個人差があり、すべての患者さんに効くわけではありません。また、使用する薬剤や患者さんの体質によっては副作用が強く出ることもあり、治療の継続に支障をきたす場合もあります。
膀胱がんは早期発見が大切
膀胱がんは、早い段階で見つけられるかどうかが、その後の治療成績や生活の質を大きく左右します。
早期の膀胱がんであれば、TURBTや膀胱内注入療法といった体への負担が少ない治療法を選択でき、良好な経過が期待できるでしょう。
しかし発見が遅れてしまうと、膀胱の摘出や薬物療法、放射線治療などの比較的負担が大きい治療が必要となり、再発や転移のリスクも高まります。
膀胱がんの代表的な症状は血尿ですが、「疲れのせい」「一時的なもの」などと見過ごされるケースも少なくありません。
そのため、尿に異変を感じたら早めに泌尿器科を受診し、必要に応じて検査を受けるようにしましょう。
生存率はあくまで「平均値」予後を良くするためにできること
膀胱がんの生存率は「平均値」であり、一人ひとりの将来をそのまま示すものではありません。
実際の予後は、治療の選択や治療後の生活習慣、そして定期的な検査をどれだけ続けられるかによって大きく変わります。
自分でできる対策を知って、予後改善に向けて行動しましょう。
生活習慣を見直す
膀胱がんの予後を良くするためには、治療だけでなく日常生活の過ごし方も大切です。
なかでも喫煙は膀胱がんの大きなリスク要因であり、治療後の再発にも深く関わっています。
また、食事では塩分を控え、野菜や果物を積極的に摂ることで、膀胱がんをはじめとしたがん全体の予防に効果的です。
さらに、適度な運動は血流を良くし、治療後の体調維持にも役立ちます。
生活習慣の改善は一度に完璧を目指す必要はなく、小さな積み重ねが将来の予後を大きく左右します。
長期的に膀胱がんと向き合うために、無理なく続けられる範囲で少しずつ改善していきましょう。
経過観察を怠らない
膀胱がんは再発しやすいため、治療が終わっても定期的な経過観察が欠かせません。
初期に見つかって治療が成功しても、数年以内に新しいがんが発生する場合もあります。そのため、膀胱鏡検査や尿検査を定期的に受け、再発や進行を早期発見することが必要です。
たとえ症状がなくても、検査でしかわからない小さながんが隠れていることがあるため、「調子が良いから検査は不要」と自己判断しないようにしましょう。
がんリスクチェックを活用する
生存率はあくまで平均値であり、自分自身の予後は生活習慣や体質、検査の受け方によって大きく変わります。
そのため、客観的に自分の体の状態を知る手段として「がんリスクチェック」を活用するのも有効です。
最近では、複数のがんリスクを一度に調べられる検査もあり、膀胱がんだけでなく他のがんの早期発見にもつながります。
大切なのは「調べて終わり」ではなく、結果をもとに行動につなげることです。
こうした検査で自分のリスクを知り、生活習慣の改善や定期検査の必要性を意識するきっかけにしてみてください。
10種類のがんリスクをチェックできる「マイシグナル・スキャン」
がんは「症状がないから大丈夫」と思っていても、実際には体の中で静かに進行しているケースも少なくありません。
そこで役立つのが、自宅で受けられるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」です。
マイシグナル・スキャンは、膀胱がんを含む膵臓・胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・前立腺の10種類のがんリスク※をステージ1から検出できます。
検査の手順は、自宅で専用キットで尿を採取して送るだけ。医療機関に行かなくても自宅で完結し、検査結果は専用のWebページで確認できます。
忙しい方や、病院に行くのをためらう方でも利用しやすいのが特徴です。
現在のがんリスクを知ることは、生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関での精密検査につなげるための第一歩になります。
未来の健康を守るために、マイシグナル・スキャンを活用してみてはいかがでしょうか。
※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。
- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
膀胱がんの予後は早期発見と日々の習慣で変えられる
膀胱がんは再発しやすい特徴を持っていますが、早期に見つければ体への負担が少なく、良好な経過が期待できます。
症状がなくても定期的な検査を受けることや、生活習慣を見直すことが予後の改善につながるでしょう。
「病院に行くほどではない」と感じている方や、家族にがんの経験者がいて不安を抱えている方には、自宅で受けられるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」という選択肢もあります。
まずは自分のリスクを知り、前向きに健康管理をはじめてみましょう。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。
- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター
急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。
自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆
カテゴリから探す
キーワードから探す