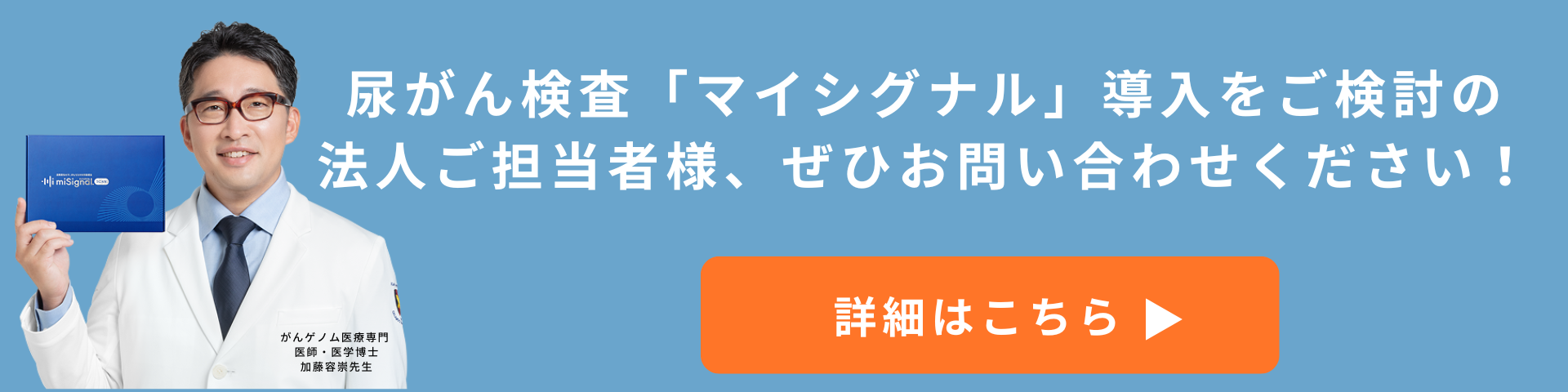活用事例
従業員が自身の健康リスクを直視するきっかけに。尿がん検査を福利厚生として導入【古賀オール株式会社】
- 公開日: 3/24/2025
- |
- 最終更新日: 7/29/2025

(古賀オール株式会社取締役副社長CEO 古畑氏)
古賀オール株式会社
所在地:東京都中央区
業種: 鉄鋼商社
従業員数:250名
導入検査:マイシグナル・スキャン、マイシグナル・ライト、マイシグナル・ナビ
古賀オール株式会社は、創業78年の鉄鋼商社として主に工作機械や自動車、住宅メーカー向けに鋼板を製造・販売しています。自社でコイルから鋼板をつくる生産設備を持ち、多様化するニーズに即した製品を供給できる点が強みです。
同社では、事業の持続可能性を高める観点で尿がん検査マイシグナルを導入。従業員272名のうち希望者全員ががんリスクを把握できるよう、福利厚生を整備しました。
今回は、古賀オール株式会社取締役副社長CEOの古畑輝英氏に、マイシグナル導入の背景や活用方法についてお話を伺いました。
従業員一人ひとりが健康リスクに対処するため導入
──「マイシグナル®️」を導入した理由ときっかけを教えてください。
古畑氏:数年前に役員合宿をした際、50代の役員が「喉が引っかかる感じがする」と話していました。当日は「早く病院に行った方がいいですよ」と雑談した程度だったのですが、それから約半年後、食道がんで亡くなりました。
もっと早く対処できていたら、結果が変わったかもしれません。日本人が生涯でがんに罹患する確率は50%以上とされています。従業員の健康管理に課題を感じていた中、7がん種の現在の罹患リスクを検査する「マイシグナル・スキャン」を知り、導入を決めました。
──やはり経営の観点においても、従業員の健康リスクを把握して対処することは重要でしょうか。
古畑氏:当社は数少ない独立系の鉄鋼一次商社で、超重量級の鋼板を製造・販売しています。鋼板の製造は500kgまではロボットアームによる自動化が進みつつありますが、当社が扱う10t以上の製品は人手が不可欠です。
労働人口不足が深刻な今、サプライチェーンに加わる企業として「本当にサステナブルなことは何か」と考えた結果、従業員一人ひとりが自身の健康状態を知り、異常があれば早期に対処するのが重要だと思いました。
最近は社会課題に対応するための福利厚生サービスが増えてきました。マイシグナルもその1つです。導入する企業が増えることで、社会全体としてより良い方向に進むのではないでしょうか。個人と企業が変われば、日本が変わるはずです。
会社負担で検査しやすく
──マイシグナル導入後、反響はいかがですか。
古畑氏:受検した従業員に今のところ高リスクの該当者は少なく、「健康について改めて考えることができた」「安心した」との反応が多いです。副次的な効果ではありますが、リスクを把握して早期に対応する姿勢を身につけることにもつながっています。
人は誰しも都合の悪い事実からは目を背けたいもの。特に40代以降は、自身の健康状態について知ることが怖くなってくるはずです。それでも直視して、リスクの芽を摘む行動につなげてほしいと思っています。この姿勢は、仕事にも求められるはずです。
──従業員全員に福利厚生として浸透させるにあたって、ハードルはありましたか。
古畑氏:がんは早期発見が大切とはいえ、自覚症状がない段階で個人がコストを負担する気にはなりにくいです。そのため、マイシグナルは会社が福利厚生として採用しました。初めは40代以上限定で導入し、後に希望者全員が受けられるように変更しています。
財務面でハードルはありますが、従業員が健康で働き続けられるようになったり、採用面で手厚い福利厚生がアピールポイントになったり、メリットも多いです。導入の際の社内調整は、経営陣の腕の見せどころですね。
テクノロジーでがん対策できる時代に
──最後に、マイシグナルの活用について、今後の展望を教えてください。
古畑氏:VUCAの時代と言われて久しいですが、予測不可能な中でもテクノロジーが答えを教えてくれるものはあります。がんに対しても、AI技術やマイクロRNAから導かれる打ち手があるなら不確実性が減り、早く対策できます。
がんの早期発見は企業単体で健康経営に盛り込む項目というよりは、社会規模で対策すべき課題である気もします。あらゆる企業で導入が進むことを祈りつつ、当社としては今後も年1回の検査を周知し、従業員が健康を見つめ直せるようフォローしていきます。
──貴重なお話をありがとうございました。

- ※マイシグナルシリーズは医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に代わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。
この記事をシェア
この記事の監修者

博士(薬学)、薬剤師
京都大学薬学部卒業。東京大学大学院 薬学系研究科にて博士号(薬学)取得。アストラゼネカ株式会社のメディカルアフェアーズ部門にて、新製品の上市準備、メディカル戦略策定、研究企画、学術コミュニケーション等を経験後、Craifにて事業開発に従事。
カテゴリから探す
キーワードから探す