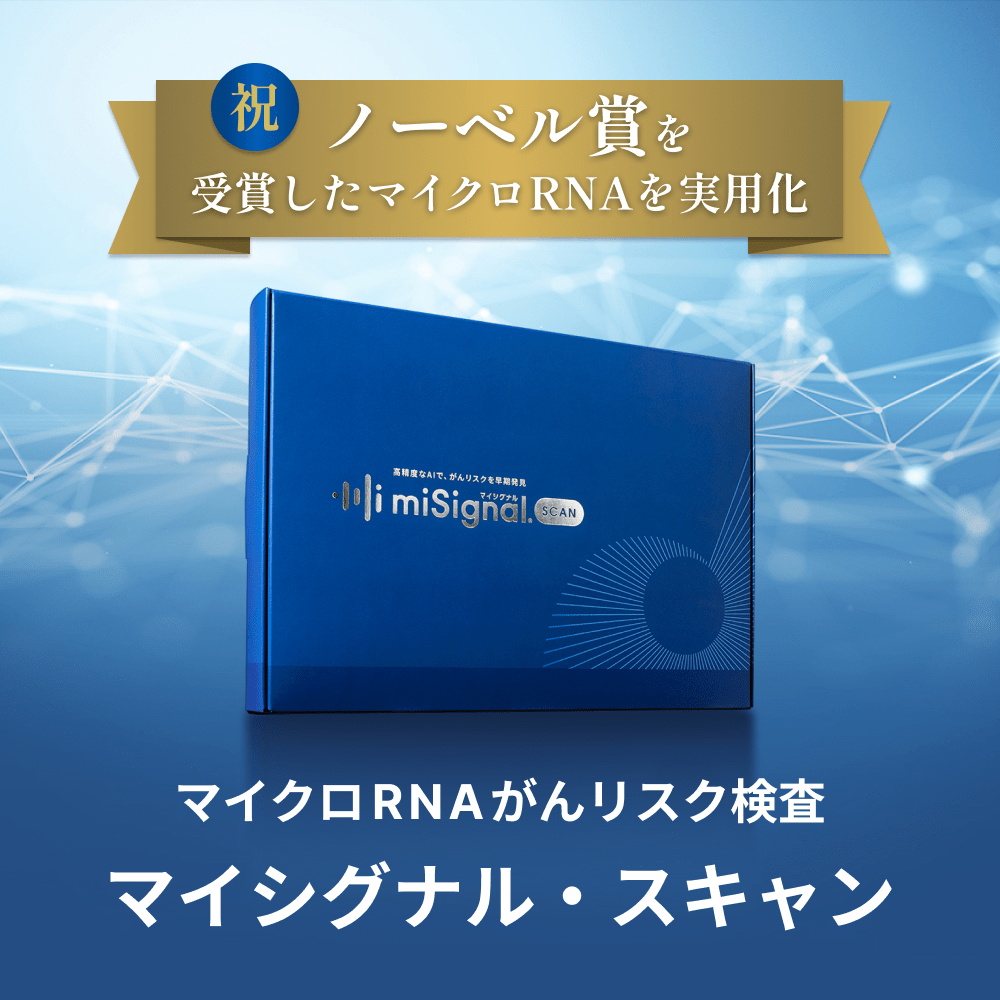がんの症状
膵石(すいせき)とは?原因や症状、膵がんとの関連性をわかりやすく解説
- 公開日: 6/22/2025
- |
- 最終更新日: 6/22/2025

なんとなく続く腹痛や消化不良で検索をしているなか「膵石(すいせき)」がヒットし、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「膵石とは?」「自然に消えるの?」「胆石との違いは?」といった疑問が浮かぶのも不思議ではありません。
この記事では、膵石の基礎知識(原因・症状・治療法・予防法)に加え、膵臓がんとの関連性や、不安な方に向けた「自宅でできるがんリスクチェック」についても丁寧に解説します。
不安を少しでも軽くし、正しい知識と向き合う一歩となれば幸いです。
目次
膵石とは?
膵石とは、膵臓の膵管内にできる硬い塊状の物質で、膵液に含まれる成分が固まってできる結石のことを指します。
膵液の流れが滞ることで膵液中のたんぱく質が凝集し、そこにカルシウムが沈着して形成されると考えられています。
膵石の原因
膵石は、ほとんどのケースで慢性膵炎が原因として形成されます。
慢性膵炎の原因は約70%がアルコールの摂取であり、その他自己免疫性や膵管の走行異常などが原因の場合もあれば、原因不明な特発性の場合もあります。
なお、膵石が見つかった場合には、診断基準上「慢性膵炎の確診例(確定)あるいは準確診例(ほぼ確定)」と判断されます。
つまり、膵石の出現は慢性膵炎の診断において非常に重要な所見となります。
胆石との違い
膵石と胆石は、どちらも「石」が体内にできる病気ですが、それぞれできる場所・成分・原因などが異なります。
| 膵石 | 胆石 | |
| 発生部位 | 膵管 | 肝臓や胆嚢・胆管 |
| 主成分 | カルシウムやたんぱく質 | コレステロールやビリルビン |
| 原因 | 慢性膵炎等 | 胆汁成分のバランスの乱れ等 |
膵石の症状と合併症リスク
膵石は膵液の流れを妨げ、さまざまな症状や合併症を引き起こすおそれがあります。
ここでは、膵石の症状やその合併症、放置した場合のリスクについて詳しく解説します。
膵石症の主な症状
膵石症の症状は人によって異なり、激しい腹痛を感じる場合もあれば、症状がない場合もあります。
一般的に、膵石が膵管内に詰まることで膵液の流れが妨げられ、腹痛や背中に痛み(背部痛)が発生します。
とくに食後や飲酒後に症状が現れることが多く、前かがみの姿勢をとることで痛みが軽減するのが特徴です。
膵石ができる主な原因である慢性膵炎では「腹痛」「背中の痛み(背部痛)」「食欲不振」「悪心 ・ 嘔吐」「下痢」「体重減少」などの症状が現れることがあります。
こうした症状をきっかけに病院を受診し、結果として膵石が見つかることも少なくありません。
膵石を放置したときのリスクは?合併症について
膵石を放置することは、慢性膵炎を放置することと同じです。
膵石自体が慢性膵炎の合併症であるため、慢性膵炎に準ずる形で以下の合併症が挙げられます。
- 膵がん
- 急性膵炎
- 膵仮性嚢胞
- 膵液瘻(膵性胸腹水を含む)
- 消化管狭窄
- 門脈圧亢進症(門脈血栓症を含む)
- 閉塞性黄疸
- 消化吸収障害
- 膵性糖尿病
- hemosuccus pancreaticus など
膵石の治療は必要?手術・内視鏡・経過観察の判断基準

膵石が見つかった場合、症状の有無や膵石の位置、合併症の有無などを総合的に判断して「経過観察」「内視鏡治療」「外科的手術」の選択肢のいずれかになります。
膵石が見つかったとしても合併症や疼痛がなければ経過観察になります。
一方、腹痛や背部痛などの症状があり、主膵管に膵石がある場合は、ESWL(体外衝撃波砕石療法)や、内視鏡治療(内視鏡的膵石除去)が検討されます。
ただし、以下のようなケースでは内視鏡による治療が難しく、外科的手術が検討されることもあります。
- 多数の膵石(多発結石)が存在する場合
- 石が膵管の形に沿って硬く固まっている場合
- 慢性膵炎により十二指腸や胆管が狭窄している場合
- 膵がんを合併していることが判明した場合
自然に膵石が消えることはある?
膵石が自然に消えることは非常にまれです。多くの場合、時間の経過とともに石は大きくなり、その他合併症につながるリスクが高まるため、症状や膵石の状態に応じた選択肢が必要となります。
膵石の治療方法
内科的治療方法
膵石の内科的治療として、主に「内視鏡治療」および「ESWL(体外衝撃波結石破砕術)」が検討されます。
内視鏡治療
内視鏡治療には「内視鏡的膵管口切開術(EPST)」「膵石除去術」「膵管ステント留置術」の3つが主な方法となっており、それぞれ治療の目的が異なります。
| 治療法 | 目的 | 適応場面 |
| 内視鏡的膵管口切開術(EPST) | 膵液の出口を切開し、膵液の流れを良くして膵石を取り出しやすくする | 膵管が狭く、膵石の取り出しが困難な場合 5mm 以下の膵石に適応 |
| 膵石除去術 | 内視鏡で器具(バスケット鉗子など)を挿入し、膵石を直接取り除く | ESWL後の補助 |
| 膵管ステント留置術 | 狭くなった膵管にプラスチック製の細い管(ステント)を入れて膵液の流れを改善 | 膵管の狭窄、膵石が膵管を塞いで膵液の流れが悪化している場合膵管の閉塞を一時的に解消する必要がある場合 |
ESWL(体外衝撃波結石破砕術)
ESWL(体外衝撃波結石破砕術)は、体の外から膵石に衝撃波を当てて、細かく砕く治療です。
砕かれた膵石は、膵液とともに自然に排出されるか、内視鏡で取り除きます。ただし、ESWLは「妊娠中の方」「腹部大動脈瘤を有する方」「明らかな出血傾向がある方」「心臓ペースメーカーを装着している方」には禁忌とされています。
外科的治療方法
内科的治療が効果を示さなかった場合、あるいは内科的治療が適さずに高度な膵管狭窄や多発結石、膵性胸腹水などの合併症がある場合には、外科的治療が適応となります。
外科的治療には「膵管減圧術」と「膵切除術」があります。
膵管減圧術は、膵管の内圧を下げるための手術です。膵液が流れにくくなり主膵管が拡張していると診断された場合に行われます。
膵管減圧術では対応が難しい場合に、狭窄部分を含む膵臓の一部を切除する膵切除術 が行われます。
外科的治療は体への負担(侵襲)が大きいものの、内視鏡治療よりも長期的な痛みの軽減率が高く、再治療の必要性が低いことが明らかになっています。
膵石の再発予防法
膵石の多くは慢性膵炎を背景としており、なかでもアルコール性膵炎が主な原因とされています。そのため禁酒することが再発の予防に効果的といえるでしょう。
喫煙も膵炎や膵石のリスクを高めるため、禁煙が推奨されます。食事では「脂肪」の摂取に注意が必要です。脂肪の摂取量は、膵石による腹痛などの症状があるかどうかによって調整が必要となります。
症状がある場合は、膵臓への負担を減らすために脂肪の摂取を制限する必要がありますが、痛みなどがない場合は1日40g〜70g(日本人の平均脂肪摂取量は約60g/1日)程度を目安としましょう。
まとめ|膵石とがんの関係性も知っておきたい。不安を減らす“今できるがんリスクチェック”
膵石は、慢性膵炎と深く関わっており、進行することで膵がんのリスクが高まることも知られています。
そのため、今は大きな症状がなくても「このままで大丈夫なのか?」という不安を抱える方も少なくありません。
そこでおすすめしたいのが「マイシグナル・スキャン」です。
「マイシグナル・スキャン」は、唾液や尿だけで複数(大腸・肺・胃・乳房・卵巣・すい臓・食道)のがんの現在のリスクをチェックできる検査キットです。
不安な気持ちを抱えたままにせず、まずは自宅で“今できるチェック”からはじめてみませんか?
\すい臓がんもステージ1から/
尿でがんのリスク検査
「マイシグナル・スキャン」
尿のマイクロRNAを調べ、がんリスクをステージ1から判定。早期発見が難しいとされるすい臓がんをはじめ、日本のがん死亡総数の約8割を占める10種のがんリスク※を、⼀度でがん種別に調べます。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター
急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。
自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆
カテゴリから探す
キーワードから探す