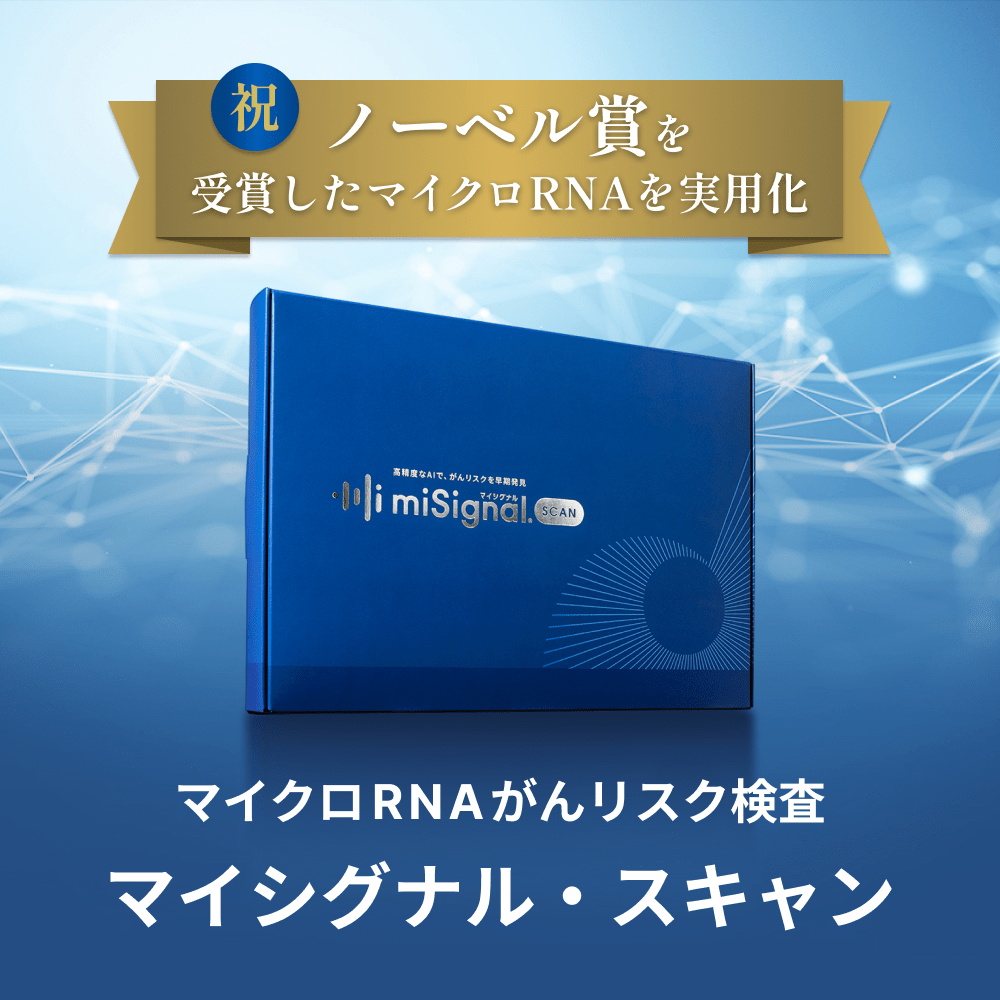がんの症状
膵炎とは?急性膵炎と慢性膵炎の違いや膵臓がんとの関係をやさしく解説
- 公開日: 6/30/2025
- |
- 最終更新日: 6/30/2025

膵炎と聞くと、「怖い病気」という印象を抱く方が多いかもしれません。
たしかに、膵炎は進行すると膵臓がんにつながるリスクがあるため、軽視できない病気です。
しかし、膵炎の種類や症状を正しく理解し、早期に適切な対処をすることが予防につながります。
本記事では、膵炎の基本的な仕組みや急性膵炎と慢性膵炎の違い、膵臓がんとの関係について詳しく解説します。
そして、「自分は大丈夫だろうか?」と不安を感じている方に向けて、自宅で簡単にできるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」について紹介します。
\すい臓がんもステージ1から/
尿でがんのリスク検査
「マイシグナル・スキャン」
尿のマイクロRNAを調べ、がんリスクをステージ1から判定。早期発見が難しいとされるすい臓がんをはじめ、日本のがん死亡総数の約8割を占める10種のがんリスク※を、⼀度でがん種別に調べます。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
目次
膵臓の役割とは?
膵臓は胃の後ろにある20cmほどの臓器であり、外分泌機能と内分泌機能の両方を持っています。
| 外分泌機能 | 内分泌機能 | |
| 役割 | 食物の消化を助ける酵素を分泌し、栄養素を吸収しやすくする | 血糖値を調整するホルモンを分泌し、均衡を保つ |
| 分泌物 | アミラーゼ(炭水化物分解) リパーゼ(脂肪分解) トリプシン(タンパク質分解) | インスリン(血糖低下) グルカゴン(血糖上昇) ソマトスタチン(インスリンとグルカゴンの分泌を抑制) |
膵臓は、消化と血糖の調節に関わる重要な役割を担っており、機能が低下すると消化不良や糖尿病などをはじめ、さまざまな疾患を引き起こすリスクが高まります。
*中外製薬 すい臓
*国立がん研究センター 東病院 膵臓の病気と治療について
膵炎とは?症状とタイプ別の見分け方
膵炎とは、膵臓が炎症を起こす病気で、「急性膵炎」と「慢性膵炎」の2種類にわけられます。
両者は原因や症状が異なり、急性膵炎は早期の治療が必要とされ、慢性膵炎は継続的な管理が求められます。
急性膵炎
急性膵炎は、膵臓の消化酵素がなんらかの原因で膵臓内で活性化し、自分自身の膵臓を消化してしまい急激な炎症が起こる病気です。
急性膵炎の最も一般的な症状は、「激しい腹痛」です。腹痛の部位としては上腹部(心窩部)や腹部全体が多く、背部まで痛みが広がる場合もあります。また、「嘔吐」「食欲不振」「発熱」も急性膵炎の典型的な症状です。
しかし、これらの症状は他の消化器系の疾患にも共通しており、急性膵炎に特有のものではありません。
急性膵炎は重症化すると、膵臓が壊死したり、周りの組織に炎症が広がったりするおそれがあり、外科的治療が必要となることもあります。
急性膵炎は早期に治療しないと生命に関わる危険が伴うため、これらの症状がある場合は直ちに医師の診察を受ける必要があります。
*急性膵炎診療ガイドライン2021
*一般社団法人 日本肝胆膵外科学会 急性膵炎と慢性膵炎
慢性膵炎
慢性膵炎は、膵臓に長期的な炎症が続くことで、膵臓の機能が徐々に失われる病気です。慢性膵炎の進行は「代償期」「移行期」「非代償期」の3段階にわけられ、各ステージで現れる症状が異なります。
代償期(初期)に主にみられる症状は「腹痛」で、この段階では膵臓の内外分泌機能は比較的保たれています。しかし、移行期や非代償期に進行すると、「体重減少」「腹部の不快感」「糖尿病」「脂肪便」といった症状が現れ、膵臓の内外分泌機能も次第に低下します。
慢性膵炎は、初期症状から糖尿病や脂肪便が現れるまでに平均約5年かかるといわれていますが、進行性の病気であるため定期的な医療的管理が必要です。
*慢性膵炎診療ガイドライン2021
*近畿大学病院 慢性膵炎の治療
膵炎になる原因とリスク因子
膵炎になる原因とリスク因子は以下の3つです。
- 生活習慣
- 疾患や薬剤の影響
- 遺伝的要因
それぞれ解説していきます。
生活習慣
膵炎の主な原因のひとつとして、生活習慣が深く関わっています。
とくに、過度の飲酒は、急性膵炎と慢性膵炎の両方を引き起こす主な原因です。
高脂肪食の摂取も膵臓に悪影響を与える要因です。膵臓に負担をかけないためには、脂肪の摂取量を抑えた食事を心がけましょう。
また、慢性膵炎の発症においては、喫煙との関連もあります。
膵炎のリスクを減らすためには、適度な飲酒や禁煙、バランスの取れた食生活が大切です。
*EAファーマ株式会社 慢性すい炎患者さんのためのすい臓にやさしい食事と生活習慣
疾患や薬剤の影響
膵炎の発症には、胆石や高脂血症、膵石などが関与することがあります。
とくに女性の場合、急性膵炎の原因として胆石症が占める比率は約37.7%です。胆石が膵管の出口を塞ぐことで膵液の流れが悪くなり、膵炎を引き起こします。
血中の脂質が増加する高脂血症でも、膵臓に負担がかかり急性膵炎を引き起こすリスクが高まります。
また、膵石は慢性膵炎の進行によって膵管内に形成することがあり、膵管を塞いだり、膵臓内での分泌物の流れを妨げたりすることで、膵臓の機能がさらに悪化することがあります。
さらに、薬剤の影響も無視できません。抗てんかん薬や免疫抑制剤、ステロイド薬などが膵臓に影響を与えることがあり、薬剤性膵炎として急性膵炎を発症することがあります。
遺伝的要因
遺伝的要因も膵炎のリスクに影響を与えることがあります。
とくに、「カチオニックトリプシノーゲン(PRSS1)遺伝子」や「膵分泌性トリプシンインヒビター((SPINK1))遺伝子」が変異している場合、遺伝性膵炎を発症しやすくなるといわれています。
遺伝性膵炎は、幼少期に急性膵炎を繰り返し、その後慢性膵炎に移行する傾向があります。
家族内に膵炎の患者が多い場合、遺伝性膵炎の可能性がありますが、遺伝子の変異があるからといって必ずしも膵炎を発症するわけではありません。
膵炎の検査方法
膵炎の検査方法は急性膵炎と慢性膵炎で異なりますが、どちらも早期の発見と治療が大切です。
以下に、急性膵炎と慢性膵炎の主な検査方法についてまとめました。
| 検査方法 | 急性膵炎 | 慢性膵炎 |
| 血液検査 | リパーゼ 膵アミラーゼ ビリルビン AST ALT ALP | 膵アミラーゼ リパーゼ トリプシン エラスターゼ1 |
| 画像検査 | 腹部超音波検査 CT MRI/MRCP | 腹部単純 X 線 CT MRI/MRCP 超音波内視鏡(EUS) 内視鏡的逆行性胆道膵管造影法(ERCP) |
| その他の検査 | なし | 細胞診組織診 |
急性膵炎は迅速な診断と治療が求められる一方で、慢性膵炎は長期にわたる管理が必要です。どちらも、医療機関で専門医の指示のもと、適切な検査を受けることが大切です。
膵炎の治療方法
急性膵炎と慢性膵炎では治療方法が異なり、膵臓の状態や重症度に応じて決定します。
それぞれの主な治療方法については、以下の通りです。
| 急性膵炎 | 慢性膵炎 | |
| 治療方法 | 絶食による膵臓の安静 点滴 薬物療法 ERCP/EST 手術 | アルコールの摂取制限 禁煙 食事管理 薬物療法 ERCP/EST 手術 |
急性膵炎の場合、主に初期治療として点滴と痛み止めを使用し、症状が落ち着くまで入院が必要です。
胆石が原因で急性膵炎が起きている場合には、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)やEST(内視鏡的乳頭括約筋切開術)を使用し、胆石の除去を行うこともあります。
慢性膵炎では、痛みの管理と食事制限を中心に、長期的な生活習慣の改善が必要とされます。
どちらも早期に治療を開始することが回復を早め、膵臓の機能維持につながります。
慢性膵炎と膵臓がんの関係
慢性膵炎が長期間続くと膵臓の細胞が傷つき、膵臓がんのリスクが高まります。
健常者と比較して、慢性膵炎患者は膵臓がんのリスクが16.5倍に高まるといわれています。
慢性膵炎が進行すると膵臓がんのリスクが高まることは確かですが、必ずしも膵臓がんを引き起こすわけではありません。
実際、慢性膵炎を抱えていても膵臓がんを発症しないケースは多く存在します。
*第52回 日本消化器がん検診学会 大会 慢性膵炎から膵臓癌
膵臓がんのリスクを知るなら「マイシグナル・スキャン」
膵臓がんは、発見が非常に難しいがんのひとつです。症状が現れる頃にはすでに進行している場合が多く、発見が遅れると治療の選択肢が限られてしまいます。
実際、市区町村のがん検診では膵臓がんを対象とした検査がなく、早期発見が難しいのが現実です。
そのような膵臓がんの早期発見に役立つのが「マイシグナル・スキャン」です。
「マイシグナル・スキャン」は、膵臓をはじめ、大腸・肺・胃・乳房・卵巣・食道の7種類のがんリスクを検出できる検査です。
ステージⅠおよびⅡAの膵臓がんを92.9%の感度で発見できたと報告されており、早期段階での検出に優れています。
マイシグナル・スキャンは自宅で尿を採取して送るだけなので、忙しくて検診に行く時間がない方でも手軽に検査可能です。
自身のがんリスクが気になる方や、忙しくてなかなかがん検診に行く時間が取れない方は、自宅でできるがんリスクチェックという選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
膵炎に関するよくある質問
膵炎に関して、よくいただく質問に回答します。
- 急性膵炎の入院期間はどれくらいですか
- 膵炎と糖尿病は関係ありますか
膵炎について正しく理解し、根拠のない不安を解消しましょう。
急性膵炎の入院期間はどれくらいですか
急性膵炎の入院期間は、軽度の場合で約1~2週間程度、重症の場合は1~2か月にわたることがあります。
重症度や合併症の有無によって入院期間は異なるため、医師の指示に従って適切な治療を行いましょう。
膵炎と糖尿病は関係ありますか
膵炎と糖尿病には深い関係があります。
膵臓は、消化酵素を分泌する外分泌機能と、血糖値を調整するホルモンを分泌する内分泌機能を持っています。内分泌機能の一部であるインスリン分泌が障害されることで、血糖値を調節できなくなり、糖尿病を引き起こす可能性があります。
とくに慢性膵炎患者では、膵臓の機能が低下することで糖尿病のリスクが高くなります。
まとめ|膵炎と診断されたら。がんリスクの“今”を見える化するという選択肢
膵炎は急性膵炎と慢性膵炎で症状や治療法が異なりますが、どちらも早期の発見と治療が大切です。
急性膵炎は迅速な治療が求められ、放置すると重症化のリスクがあります。一方、慢性膵炎は時間をかけて膵臓の機能が低下するため、継続的な管理が大切です。
慢性膵炎が長期間続くと、膵臓がんのリスクが高まることもあります。
膵臓がんは早期発見が難しいため、自宅で簡単にできるがんリスクチェック検査「マイシグナル・スキャン」を活用するのも有効です。
適切な検査と生活習慣の見直しを行い、膵臓がんはじめ、さまざまなリスクを減らしましょう。
\すい臓がんもステージ1から/
尿でがんのリスク検査
「マイシグナル・スキャン」
尿のマイクロRNAを調べ、がんリスクをステージ1から判定。早期発見が難しいとされるすい臓がんをはじめ、日本のがん死亡総数の約8割を占める10種のがんリスク※を、⼀度でがん種別に調べます。
- ※ 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター
急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。
自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆
カテゴリから探す
キーワードから探す