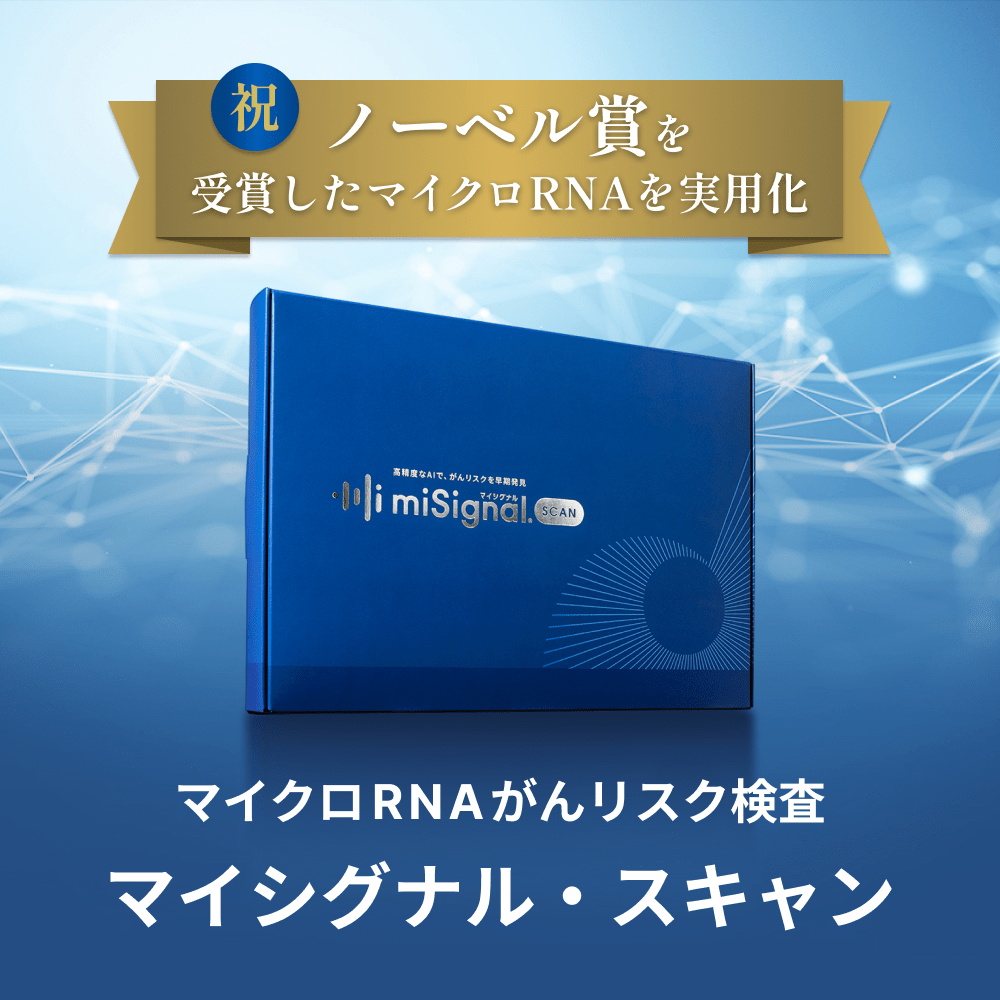がん検査
がんの症状
膵臓がんが発覚したきっかけは?初期サインと見逃さないための対策を解説
- 公開日: 7/25/2025
- |
- 最終更新日: 7/28/2025

膵臓がんは初期症状の少なさから発見が遅れることが多く、早期発見が難しいがんのひとつです。
しかし、背中の痛み・急な体重減少・定期健診などがきっかけで見つかるケースもあります。
本記事では、膵臓がんが発覚する主な4つのパターンと、見逃してはいけない症状をわかりやすく解説します。
さらに、病院での精密検査に進む前に“今の自分のがんリスク”を知るための選択肢として「マイシグナル・スキャン」もご紹介。
がんに対して少しでも不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
膵臓がんが発覚するきっかけ4選を紹介
膵臓がんは、症状による受診以外に、健康診断や病院での検査をきっかけに偶然発見されるケースもあります。
実際に膵臓がんが発見された事例を参考にして、自身の健康管理に役立ててみてください。
症状で発覚したケース
膵臓がんは初期症状がほとんどないため、発覚時にはすでに進行しているケースも少なくありません。
進行にともない、以下の症状が現れることがあります。

- みぞおちや背中の痛み
- 食欲不振
- お腹の張り
- 体重減少
- 黄疸
しかし、膵臓がんの症状は他の病気でも見られるものが多く、見逃されやすいのが特徴です。
複数の症状がある場合や、原因不明の体調不良が続く場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
健康診断で発覚するケース
定期健康診断や人間ドックで行った検査が、膵臓がん発見のきっかけとなることもあります。
血液検査では、以下の項目で数値の異常が指摘された場合、膵臓になんらかの異常がある可能性があります。
| 腫瘍マーカー | ・CA19-9 ・Span-1 ・DUPAN-2 ・CEA ・CA50 |
| 膵酵素 | ・アミラーゼ ・リパーゼ |
また、腹部超音波検査などの画像検査で、膵臓に異常が見つかることもあります。腹部超音波検査では、膵臓の大きさや形状の異常、膵管拡張などの兆候が確認できます。
ただし、血液検査や超音波検査だけでは膵臓がんの診断は確定できません。
一部の健診施設では、「膵ドック」としてCTやMRI、MRCP検査を受けられるコースもあります。
他の検査中に偶発的に見つかるケース
膵臓がんは、他の病気の検査や治療の過程で偶然発見されることもあります。
たとえば、腹部超音波検査やCT、MRIなどを別の目的で受けた際に偶然膵臓に異常が見つかり、精密検査の結果がんと診断されるケースです。
無症状の段階で発見できた場合、比較的早期での治療が可能となる場合もあるでしょう。
リスク因子からチェックが進むケース
膵臓がんが発覚するきっかけのひとつに、リスク因子から精密検査に進むケースがあります。
膵臓がんには、以下のようなリスク因子が存在します。

- 過度な飲酒
- 喫煙
- 肥満
- 家族歴
- 糖尿病
- 膵のう胞
- 慢性膵炎
- 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)
とくに慢性膵炎、膵のう胞やIPMNがある方は、定期的に画像検査や腫瘍マーカーの測定を行うことで、膵臓がんの早期発見につながることがあります。また、糖尿病の発症や血糖のコントロール不良がきっかけで見つかるケースも少なくありません。
膵臓がんのリスク因子を持つ方は、自覚症状がない場合でも、自己判断せず医師と相談して適切なタイミングで検査を受けることが大切です。
膵臓がんの生存率
膵臓がんの生存率は、進行度や発見のタイミングに大きく影響されます。
膵臓がんの進行度別の5年生存率は以下の通りです。
| 進行度 | 5年生存率 |
| 限局 | 42.1 |
| 領域 | 12.4 |
| 遠隔 | 1.8 |
膵臓がんの5年生存率は、全体で約8.5%程度です。
しかし、膵臓がんが局所的にとどまっており手術が可能な場合、生存率は大きく改善します。一方で、進行して転移が広がっている場合は、生存率が大きく低下します。
膵臓がんの症状とは?見逃されやすいサインに注意
膵臓がんが進行することによって、以下の症状が現れることがあります。

- みぞおちや背中の痛み
- 食欲不振・体重減少・倦怠感
- 皮膚や白目の黄ばみ・かゆみ(黄疸)
膵臓がんのサインがどのように現れるか、具体的に解説していきます。
みぞおちや背中の痛み
膵臓がんの症状として、みぞおちや背中に痛みを感じることがあります。
膵臓の周りには多くの神経があるため、進行にともなって神経が圧迫されると痛みが急に強くなることもあります。
痛みが長期間続いたり、次第に痛みが強くなったりする場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
食欲不振・体重減少・倦怠感
膵臓がんでは、消化機能に関わる膵臓の働きが低下するため、食欲不振や体重減少を引き起こすことがあります。
膵臓ががんに侵されると、膵液が十分に分泌されなくなり、食事をしても栄養の吸収がうまくいかなくなるためです。
また、がんの進行にともない筋肉や脂肪が減少し、体重減少や食欲不振、強い倦怠感などが現れることもあります。
皮膚や白目の黄ばみ・かゆみ(黄疸)
膵臓がんの症状として、皮膚や白目が黄色くなったり、かゆくなったりする「黄疸」が現れることがあります。
膵臓の頭部にがんができることで胆管が圧迫され、胆汁の流れが妨げられることが原因です。胆汁に含まれるビリルビンという色素が血液中にたまり、皮膚や白目が黄色く見えるようになります。
黄疸が進行すると、尿の色が濃くなったり、便が白っぽくなったりすることもあります。
ただし、黄疸は肝硬変や胆管炎、胆管閉塞などの他の疾患でも現れるため、必ずしも膵臓がんが原因であるとは限りません。
血液検査や腹部超音波検査で異常が見つかったら
血液検査や腹部超音波検査だけで最終的な診断をすることは難しいため、追加の確認が必要となります。
異常が見つかった場合、次のステップとしてどのような対応が必要かを理解しておきましょう。
血液検査だけで膵臓がんは診断できない
膵臓がんの疑いがある場合、血液検査の結果は重要な手がかりとなります。
とくに膵臓がんを含む消化器系のがんの腫瘍マーカーとして「CA19-9」が広く使用されています。しかし、CA19-9は慢性膵炎や胆石症、糖尿病などの他の疾患でも上昇することがあるため、これだけでがんと断定することはできません。
さらに、膵臓がんのステージⅠ/ⅡAにおけるCA19-9の検出感度※1 はわずか37.5%と報告されており、早期の膵臓がんを検出するには十分ではありません。
膵酵素であるアミラーゼやリパーゼも、膵炎などの他の病気で異常を示すことがあります。
そのため、血液検査の結果はあくまで診断の補助として使用し、画像診断や他の検査と組み合わせて総合的に評価します。
- ※1 一般的に臨床で用いられる値をしきい値とした場合の数値
- *SRL総合検査案内 CA19-9
腹部超音波検査で「膵管拡張」や「しこり」を指摘されたら
外来や健康診断でよく使われる「腹部超音波検査」は、体に負担が少ない安全な検査方法です。
腹部超音波検査で膵臓に「膵管拡張」や「しこり(腫瘤)」が見つかった場合、膵臓がんをはじめとする疾患の可能性があります。
膵管拡張とは、膵液が流れる主膵管が通常より太くなっている状態です。腫瘍や膵石によって膵液の流れが妨げられることで、上流側の膵管が膨らみます。
もし腹部超音波検査で膵臓に膵管拡張や腫瘤が見つかった場合、さらに詳しい検査が必要です。具体的には、造影CT・腹部MRI/MRCP・EUS(内視鏡的超音波検査)・ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)などが推奨されます。
膵臓がんと診断される前にできること
膵臓がんと診断される前にしておくべきことは、以下の3つです。

- 病院に行くべき症状と様子を見るべき症状をチェック
- 家族歴や基礎疾患がある場合のリスク管理
- “今の状態”を知るためにできる自宅チェックの活用
膵臓がんを早期発見するために、日々の行動を意識してみてください。
病院に行くべき症状と様子を見るべき症状をチェック
膵臓がんは早期に発見することが難しく、体調に明らかな異変が生じた段階では進行している場合が多いため、早めに医療機関を受診することが大切です。
とくに、以下の症状が続いたり、悪化したりすると、膵臓に異常がある可能性があります。

- 持続的な腹痛
- 体重減少
- 食欲不振
- 皮膚や白目の黄色化(黄疸)
症状が気になるなら医師に相談し、必要に応じてCTやMRIなどの精密検査を受けましょう。
家族歴や基礎疾患がある場合のリスク管理
膵臓がんのリスクは、家族歴や基礎疾患の有無によって高まることがあります。
とくに、家族に膵臓がんを患った方がいる場合、膵臓がんのリスクが増加することが知られています。
糖尿病や慢性膵炎などの基礎疾患がある方も、膵臓がんの発症リスクが高まるため、定期的に検査を受けるようにしましょう。
また、適度な飲酒や禁煙、バランスの取れた食生活など、生活習慣の見直しもリスク管理の一環です。
定期的なリスクの評価と管理を行うことで、膵臓がんを早期に発見でき、治療の選択肢を広げることができます。
“今の状態”を知るためにできるがんリスクチェック
膵臓がんを早期発見するためには、日々の健康状態を意識することも有効です。
たとえば、体重や食事量の変化、お腹の張りをチェックすることなどがあげられます。
食後の不快感や消化不良が続く場合には、経過を記録しておくことで、異常の早期発見につながるでしょう。
さらに、膵臓がんの不安を軽減したい場合には、がんリスクを自宅でチェックできる「マイシグナル・スキャン」という選択肢もあります。
自身の体調に関心を持ち、変化を正確に把握することが、膵臓がんの早期発見につながります。
自宅でできる膵臓がんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」
膵臓がんは早期発見が難しく、症状が出たときにはすでに進行しているケースが多いのが現実です。
だからこそ、症状がないうちから、定期的ながんのリスクチェックを自宅で手軽にできる新しい検査法が注目されています。
ここからは、膵臓がんをはじめとする複数のがんリスクを一度に調べられる「マイシグナル・スキャン」についてご紹介します。
マイシグナル・スキャンとは?
「マイシグナル・スキャン」は、自宅で簡単にできるがんリスク検査です。
膵臓がんを含む、胃・大腸・肺・乳房・卵巣・食道・腎臓・膀胱・前立腺の10種類のがん※を同時に検査できます。
自宅で尿を採取するだけなので、痛みや負担を感じることなく、忙しい方でも手軽に検査可能です。
検査結果によってどの診療科で精密検査を受けるべきかも提案するなど、早期発見に加え、その後の治療へのアプローチもしっかりサポートします。
- ※卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります
どんな人におすすめ?
「マイシグナル・スキャン」は、以下の方におすすめです。

- がんのリスクに不安を感じている
- 家族にがんの既往歴がある
- 忙しくてがん検診を受ける時間がない
とくに膵臓がんは、初期段階で症状がほとんど現れません。そのため早期発見が非常に難しく、定期的なリスクチェックが重要です。
従来の検査方法では見逃されがちな膵臓がんも、尿のマイクロRNA検査では92.9%という高い感度で検出できたと報告されているため、早期発見の手助けとなります。
健診や病院での検査を受ける時間が取れない方でも、負担に感じることなく検査を受けていただけます。
病院で検査に進む前の“安心材料”としてがんリスクチェックという選択肢を丈夫?
膵臓がんが発覚するきっかけは、症状の出現や健康診断、ほかの検査中での発見など、さまざまなケースがあります。
初期症状がわかりにくく、発見が遅れることが多い膵臓がんでは、早期発見が非常に重要です。日々の健康状態を意識し、定期的なリスク評価を行うことで、早期発見の可能性が高まります。
また、自宅で簡単にできるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」の活用もひとつの選択肢です。
忙しい毎日のなかで、自宅で簡単にがんリスクを把握することができ、万が一のときも安心して次のステップに進めます。
自身のがんリスクを把握して必要な検査を受けることで、膵臓がんを含むがんの早期発見につながり、予後の改善が期待できます。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。
- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者
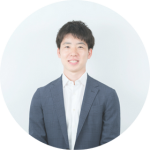
名古屋大学 未来社会創造機構 客員准教授、博士(薬学)、薬剤師
東京大学大学院 薬学系研究科にてケミカルバイオロジーを専攻し博士号(薬学)を取得。研究活動に並行してGlobal Healthのプロジェクトにも従事。幼少期をオランダで過ごした海外経験と技術バックグラウンドを活かし、米国のNPOにてザンビア等の開発途上国への医療テクノロジー導入も支援。大学院修了後、2013年にバイエル薬品に入社。オンコロジーや眼科領域事業でMR、マーケティングの経験を積んだ後、経営企画や全社プロジェクトのPMO等、幅広い業務をリードした。 同社を退職後、2019年1月Craif株式会社に参画。
カテゴリから探す
キーワードから探す