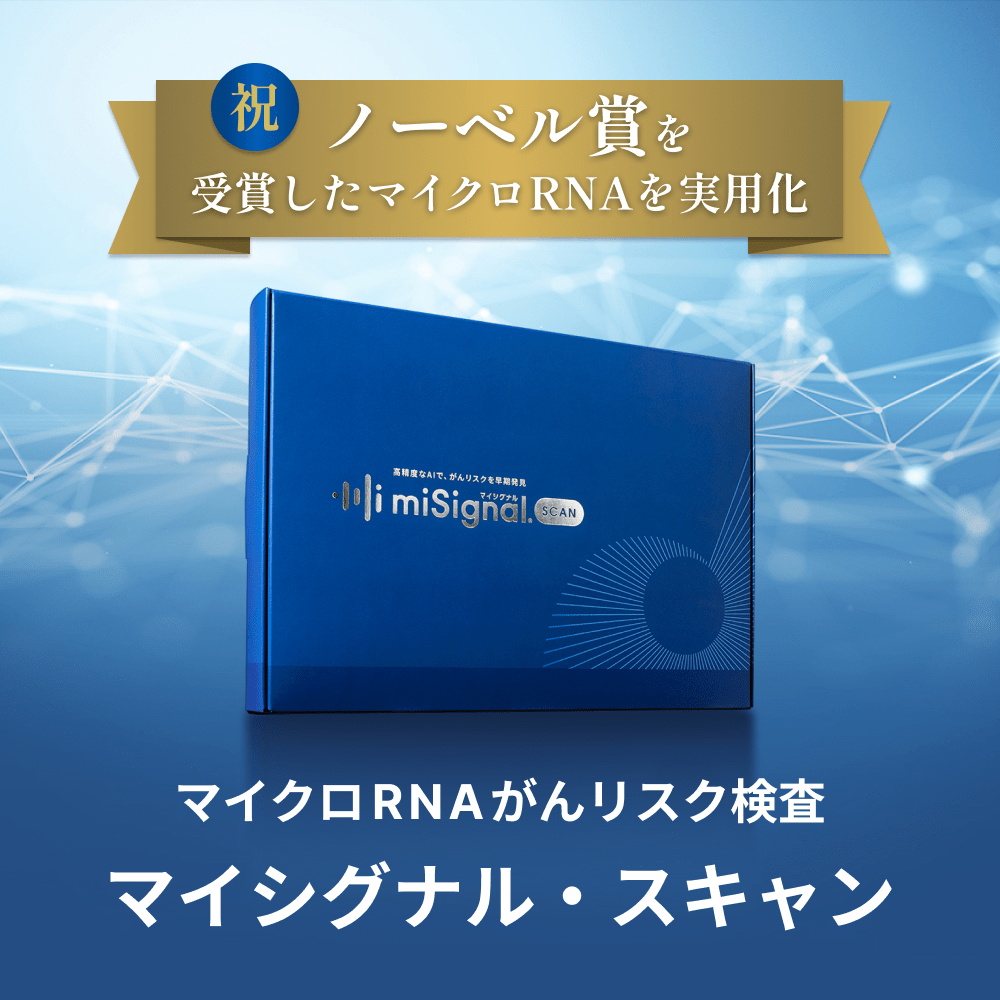がんの症状
がんの基礎情報
慢性膵炎とは?症状・原因から膵臓がんとの関係までわかりやすく解説
- 公開日: 8/25/2025
- |
- 最終更新日: 8/25/2025

慢性膵炎は、膵臓に慢性的な炎症が続く疾患です。進行すると膵機能が低下し、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があります。
将来的に膵臓がんのリスクを高める疾患としても知られているため、早期発見と適切な対応が大切です。
本記事では、慢性膵炎の症状から膵臓がんとの関係まで、わかりやすく解説します。
病院に行く前にできる“安心の選択肢”として、自宅でできるがんリスク検査についても紹介しています。
慢性膵炎について気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
慢性膵炎とは

慢性膵炎とは、膵臓でつくられた膵液が、本来働くべき十二指腸ではなく膵臓内で活性化してしまい、自らの膵臓をゆっくりと傷つけ続ける病気です。
膵臓には、食べ物の消化を助ける酵素や、血糖値を調整するインスリンなどのホルモンをつくる役割があります。
しかし、慢性膵炎が進行すると、膵臓が固くなったり、膵石(すいせき)ができたりして、本来の機能を果たせなくなります。
とくに40〜50代で発症するケースが多く、放置すると日常生活にも影響を及ぼすようになるため、早期の発見と適切な対応が必要です。
*一般社団法人 日本膵臓学会
*日本消化器病学会 患者さんとご家族のための慢性膵炎ガイド2023
急性膵炎との違い
膵炎には、急激に発症する「急性膵炎」と、慢性的に進行する「慢性膵炎」があります。
急性膵炎は、突然の激しいみぞおちの痛みが特徴です。多くの場合は適切な治療を受ければ回復しますが、重症化すると命の危険もあります。
一方で、慢性膵炎は炎症が長期間にわたって持続したり、繰り返したりすることで、膵臓の組織が線維化し、破壊されていきます。
慢性膵炎による組織の損傷は非可逆的であり、一度失われた膵臓の機能が完全に回復することはありません。
*一般社団法人 日本膵臓学会 急性膵炎・慢性膵炎に対する薬物治療
【ステージ別】慢性膵炎の主な症状
慢性膵炎は、進行の程度によって「潜在期」「代償期」「移行期」「非代償期」の4つの段階に分けられ、症状の現れ方が異なります。
ここでは、潜在期・代償期と移行期・非代償期にみられる主な症状の違いについて、詳しく解説します。
潜在期・代償期の症状
慢性膵炎の初期段階である「潜在期」や「代償期」では、膵臓の機能はある程度保たれています。
この時期の症状として、膵臓の酵素が膵臓自体を傷つけることにより、お腹や背中の痛みを繰り返します。
とくに、お酒を飲んだり、脂っこいものを食べたりすることで、痛みが起こりやすくなる傾向です。
痛みが強くなったり治まったりを繰り返しながら、膵臓の炎症は徐々に進行していきます。
移行期・非代償期の症状
慢性膵炎が進行し、「移行期」や「非代償期」になると、膵臓の機能は大きく損なわれていきます。
この時期になると、炎症による痛みは軽減する傾向です。一方で、消化酵素の分泌が著しく低下するため、脂肪便や慢性的な下痢、体重の大幅な減少といった栄養吸収の障害がみられます。
さらに、インスリン分泌の低下により糖尿病を発症するケースも少なくありません。
ただし、こうした明らかな症状が出ないまま進行する場合もあります。
進行度によっては日常生活に大きな影響が及ぶため、症状の有無に関わらず、早期の対応と定期的な経過観察が大切です。
慢性膵炎の原因とリスク因子
慢性膵炎の発症には、さまざまな要因が関わっています。
ここでは、慢性膵炎を引き起こす主なリスク因子について、わかりやすく解説します。
生活習慣
慢性膵炎の発症には生活習慣が深く関わっており、以下のような要因がリスクを高めます。
- 過度な飲酒
- 喫煙
- 脂質の多い食事
なかでも最も大きな原因としてあげられるのが「過度な飲酒」で、全体の約7割が飲酒と関連しています。
日本酒を1日に3合(アルコール量で約60g)以上飲む人は、慢性膵炎になるリスクがとくに高まるので注意しましょう。
また、脂質の多い食事も、慢性膵炎の発症につながるおそれがあります。
揚げ物やカップ麺、スナック菓子などの高脂肪食品はできるだけ控え、バランスの取れた食生活を心がけましょう。
*難病情報センター 重症急性膵炎
*EAファーマ株式会社 慢性すい炎患者さんのためのすい臓にやさしい食事と生活習慣
遺伝的要因
慢性膵炎は、遺伝的な要因も発症に関与していることがわかっています。
とくに「PRSS1遺伝子」や「SPINK1遺伝子」などの、膵臓の酵素に関係する遺伝子に変異がある場合、遺伝性膵炎を発症しやすくなります。
遺伝性膵炎は、子どもの頃から繰り返し急性膵炎のような発作を起こしやすい傾向です。家族のなかに膵炎を経験した人が複数いる場合は、遺伝性膵炎の可能性も考えられます。
ただし、遺伝子に変異があるからといって、必ずしも慢性膵炎を発症するわけではありません。
慢性膵炎の検査方法
慢性膵炎の診断は、複数の検査を組み合わせて行う必要があります。
ここでは、慢性膵炎の診断に用いられる主な検査方法と、それぞれの役割について解説します。
血液検査
慢性膵炎の検査では、まず血液検査によって膵臓の状態や炎症の有無を確認します。
具体的には、以下のような項目を測定します。
| 測定項目 | 意義 |
| アミラーゼ | 膵臓疾患のスクリーニングに有用 |
| リパーゼ | 膵管の狭窄・閉塞による膵液のうっ滞・膵臓組織の破壊を反映 |
| トリプシン | 膵臓の炎症・膵管の閉塞・膵外分泌機能の残存量の指標などを反映 |
| エラスターゼ1 | 膵外分泌機能を反映 |
慢性膵炎が進行して膵臓の機能が大きく低下すると、これらの値はかえって低値を示す場合もあります。
血液検査だけでは慢性膵炎と診断することはできないため、他の検査と組み合わせて評価する必要があります。
*SRL検査総合案内 アミラーゼ
*SRL検査総合案内 リパーゼ
*SRL総合検査案内 トリプシン
*SRL総合検査案内 エラスターゼ1
画像検査
慢性膵炎の画像検査として、以下があげられます。
| 画像検査の種類 | 特徴 |
| 腹部単純X線 | 膵石症を伴った慢性膵炎の診断に有用 |
| CT | 腹部全体の観察に有用周囲の臓器との関連を観察可能 |
| MRI/MRCP | 主膵管の変化や拡張した分枝を観察可能進行した慢性膵炎に有用 |
| 超音波内視鏡(EUS) | 膵臓に加え胆管・胆のうなどの周辺臓器まで観察可能早期慢性膵炎にも有用 |
| 内視鏡的逆行性胆道膵管造影法(ERCP) | 膵管の形態を最も詳細に観察可能必要に応じて治療も可能 |
これらの画像検査を組み合わせ、慢性膵炎の進行度や、合併症の有無を総合的に評価します。
病理検査
血液検査や画像検査で慢性膵炎が強く疑われるものの、診断が確定しない場合や、膵臓がんとの鑑別が必要な場合には、病理検査が有用です。
その際には、内視鏡的逆行性膵胆管造影(ERCP)で膵管内に細いチューブを挿入して細胞を採取したり、超音波内視鏡(EUS)で膵臓の病変を直接観察しながら針を刺して組織を採取したりします。
採取した細胞や組織を顕微鏡で詳しく調べ、炎症の程度や線維化の状態、がん細胞の有無などを確認します。
慢性膵炎の診断基準
慢性膵炎の診断は、症状・血液検査・画像検査、場合によっては病理検査の結果を総合的に評価して行われます。
日本膵臓学会が定めている診断基準は、以下の通りです。
| 慢性膵炎の診断項目1.特徴的な画像所見2.特徴的な組織所見3.反復する上腹部痛または背部痛4.血中または尿中膵酵素値の異常5.膵外分泌障害6.1 日 60 g 以上(純エタノール換算)の持続する飲酒歴または膵炎関連遺伝子異常7.急性膵炎の既往 |
| 慢性膵炎確診:a,b のいずれかが認められるa.①または②の確診所見b.①または②の準確診所見と,③④⑤のうち 2 項目以上慢性膵炎準確診:①または②の準確診所見が認められる.早期慢性膵炎:③~⑦のいずれか 3 項目以上と早期慢性膵炎の画像所見が認められる |
複数の要素を総合的に評価して慢性膵炎の診断を確定し、適切な治療へとつなげます。
慢性膵炎の治療方法
慢性膵炎の具体的な治療方法として、以下があげられます。
- アルコールの摂取制限
- 禁煙
- 食事管理
- 薬物療法
- ERCP/EST
- 手術
慢性膵炎の治療は、膵臓の炎症によるダメージを抑え、症状を和らげながら進行を遅らせることが目的です。
痛みの管理と生活習慣の改善を中心に、必要に応じて薬物療法を組み合わせて治療が進められます。
膵液の流れが妨げられている場合は、内視鏡的手技(ERCP・EST)で膵管の狭窄や結石を取り除く処置を行うこともあるでしょう。
保存的治療では改善が見込めない場合や、強い痛みが続くケースでは、手術によって膵臓の一部を切除する選択肢も検討されます。
*三重大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科(第1外科) 慢性膵炎外科治療
慢性膵炎は膵臓がんのリスクを高める
持続的な炎症によって膵臓の細胞が繰り返しダメージを受けることで、将来的に膵臓がんへ進行する可能性があります。
健康な人と比較して、慢性膵炎患者は膵臓がんの発症リスクが16.5倍に上がるといわれています。
遺伝性膵炎や、若い頃から膵炎を繰り返しているケースでは、さらにリスクが高まることもあるため注意が必要です。
膵臓がんは発見が難しいがんのひとつであり、進行してから見つかるケースも少なくありません。
そのため、慢性膵炎と診断された場合は、症状の管理だけでなく、定期的な経過観察が非常に重要です。
*第52回 日本消化器がん検診学会 大会 慢性膵炎から膵臓癌
膵臓がんのリスクチェックなら「マイシグナル・スキャン」
膵臓がんのリスクを把握するなら、がんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」という選択肢もあります。
マイシグナル・スキャンは、膵臓がんをはじめ、大腸・肺・胃・乳房・卵巣・食道・膀胱・前立腺・腎臓といった10種類のがんリスク※を、ステージ1から検出できる検査です。
検査の方法は、自宅で採尿をして送るだけ。痛みや制限がないため、ストレスを感じることなく簡単に検査を受けられます。
がん種ごとにリスクがわかるため、リスクが高く出た際の受診すべき診療科がわかりやすく、迷わず次の一歩を踏み出せます。
忙しくて病院に行く時間がない方や、膵臓がんのリスクが気になる方は、「マイシグナル・スキャン」で、日常の安心につなげてみてはいかがでしょうか。
※ 卵巣がん・乳がんは女性のみ、前立腺がんは男性のみ検査対象となります。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。
- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
慢性膵炎に関するよくある質問
慢性膵炎に関して、よくいただく質問に回答します。
- 慢性膵炎の初期症状はなんですか
- 慢性膵炎は治りますか
慢性膵炎について正しく理解し、根拠のない不安を解消しましょう。
慢性膵炎の初期症状はなんですか
慢性膵炎の初期段階では、自覚症状がないまま経過するケースも少なくありません。
初期症状がある場合は、みぞおちや背中にかけて痛みを感じることがあります。
違和感があっても放置されやすいですが、早期に発見・対応することで進行を抑えることができます。
少しでも気になる変化がある場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
慢性膵炎は治りますか
慢性膵炎で一度ダメージを受けた膵臓の組織は、完全に元の状態に戻ることはありません。
しかし、適切な治療や生活習慣の見直しにより、膵臓への負担を減らし、症状を和らげたり進行を抑えたりすることはできます。
慢性膵炎と向き合って将来のがんリスクに備えよう
慢性膵炎は、膵臓に慢性的な炎症が続き、機能が徐々に失われていく病気です。
進行すれば、日常生活に支障をきたすだけでなく、膵臓がんのリスクが高まることもわかっています。
自覚症状がないこともあるため、気づかないうちに進行してしまうケースも少なくありません。
しかし、早い段階で異変に気づき、適切な治療や生活習慣の見直しを行うことで、症状の進行を抑えながら、生活の質を保つことが可能です。
膵臓がんのリスクが気になる方には、自宅で手軽にできるがんリスクチェック「マイシグナル・スキャン」という選択肢もあります。
日々の体調に目を向けながら生活習慣を見直し、将来の健康を守る第一歩を踏み出しましょう。
\早期発見の難しいすい臓がんも対象/
「尿」で10種のがんリスクを判定!
マイシグナル・スキャン
日本のがん死亡数の約8割を占める10種類のがん※を個別にリスク判定します。尿中のマイクロRNAをAI解析技術が評価され、すでに全国2000軒の医療機関でも導入されています。
- ※国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)、ただし造血器腫瘍を除く
この記事をシェア
この記事の監修者

臨床検査技師 医療ライター
急性期病院で8年間臨床検査技師として勤務。
自身の臨床経験と確かなエビデンスを元に、医療メディアを中心として記事を執筆
カテゴリから探す
キーワードから探す